- メルマガを始めるとき「法律の理解」と「配信スタンド選び」は特に大切
- メルマガを始めたら「メルマガ登録ページ」をすぐに作る
- メルマガ登録直後に配信される「自動返信メール」をしっかり作り込む
[char no=”1″ char=”トール”]今回のテーマは『初心者にも簡単なメルマガの始め方』について![/char]
どうもー!トールです(@tooru_medemi)
メルマガって難しいイメージがあるようですが、しっかりと手順を踏んで進めていくだけ誰でも始められます。
これらの手順の中でも「メルマガ関連の法律」と「メルマガ配信スタンド」はとくに重要です。
そこで本記事では、メルマガを始める手順を「9つのステップ」で解説します。
メルマガの始め方【9ステップ】
メルマガを始める流れ9ステップを一覧表にまとめました。記事から抽出した各ステップの特徴を簡潔にまとめています。
| ステップ | 簡単な特徴 |
|---|---|
| 1. メルマガ配信の目的・目標を決める | なぜメルマガを活用するのかを明確化し、具体的な数値目標を設定する |
| 2. メルマガのターゲットを明確にする | 性別、年齢、仕事、趣味、生活リズムなどを踏まえてペルソナを設定する |
| 3. メルマガ関連の法律を確認する | 特定電子メール法や個人情報保護法の順守事項を理解し、適切な配信体制を構築する |
| 4. メルマガ配信スタンドを選ぶ | 配信数の上限、テンプレート、ステップメール機能、操作性などを比較検討する |
| 5. メルマガの読者リストを作る・増やす | 既存顧客や取引先から始めて、オプトインページを作成して質の高い読者を獲得する |
| 6. メルマガを作成する | 件名の工夫、短くわかりやすい本文、テキストメール/HTMLメールの使い分けを検討する |
| 7. メルマガの配信頻度・スケジュールを決める | ターゲット層のライフスタイルに合わせて配信タイミングと頻度を最適化する |
| 8. メルマガ配信に効果測定をする | 開封率、クリック率、CVRなどの指標を測定し、A/Bテストで改善を重ねる |
| 9. メルマガを軸に施策を広げる | 他チャンネルとの連携、ブランド戦略、ステップメール・MAツールで相乗効果を狙う |
※横スクロールで全部見れます
これらのステップは順序立てて実行することで、法的リスクを避けながら、効果的なメルマガ運用ができるように構成されています。
特に、最初の3ステップ(目的設定、ターゲット設定、法律確認)と、4ステップ目の配信スタンド選びは、後の運用に大きく影響する重要なポイントです。
メルマガを始める前に知っておきたいこと
メルマガ運用を検討する段階では、ほかのチャネルと比較しながら「どのような特徴やメリット・デメリットがあるのか」を把握しておくと、運用方針がより明確になります。
そして、それぞれのチャネルが持つ特質を踏まえ、メルマガと組み合わせることで効果を最大化できるシナリオを描くのが重要です。
| メリット | デメリット | |
| メルマガ | ・登録読者へ直接アプローチできるため、深いコミュニケーションを築きやすい ・配信タイミングや内容を細かく制御でき、PDCAを回しやすい ・一度獲得した読者リストは長期的な資産になる | ・配信停止やスパム報告など、法律面の順守が必須 ・開封率・クリック率を高めるための工夫が欠かせない ・誤配信リスクや運用コストが発生する |
| SNS | ・拡散性が高く、シェアを通じて新規ユーザーへリーチしやすい ・視覚的・瞬発的な訴求が可能(画像や短文で情報拡散) ・ユーザーとのリアルタイムなやり取りがしやすい | ・投稿が時間の経過とともに流れやすく、長期的な情報保持には不向き ・フォロワー数が少ないうちは効果が限定的 ・プラットフォームの仕様変更や規制に左右されやすい |
| YouTube | ・動画で視覚的・聴覚的に訴求でき、商品やサービスの魅力を直感的に伝えやすい ・チャンネル登録者との接触頻度が高まりやすく、ファン化を促進しやすい ・SEO対策の一環として検索表示される可能性もある | ・撮影・編集に手間やコストがかかり、継続運用のハードルが高い ・動画視聴にはある程度時間を要するため、短時間で情報を得たい層には不向き ・過激な内容や広告制限に抵触しないよう注意が必要 |
| ポッドキャスト | ・音声のみで配信できるため、通勤・作業中など「ながら聴き」に対応しやすい ・登録者やリスナーが増えればブランドの親近感が強化される ・映像を伴わないため、比較的準備が簡易 | ・テキストや動画ほど拡散力が高くない場合が多い ・音声だけでは詳細な説明が難しく、ビジュアル重視のコンテンツには不向き ・番組発見性(検索やおすすめ表示)に制限があり、認知拡大に時間がかかる |
※横スクロールで全部見れます
上記のように、それぞれのメディアには特徴的な強みと弱みが存在します。
メルマガを中心に据えつつ、これらのチャネルを補完的に運用して相乗効果を狙う方法も有効です。
特に、メルマガでイベントやキャンペーン情報を告知し、SNSで拡散、YouTubeやポッドキャストで詳しく解説する流れを構築すれば、より多くの見込み客へ多面的にアプローチできるでしょう。
[char no=”2″ char=”トール”]いずれは「他チャネル化」を目指しましょう![/char]
メルマガを始める流れ
メルマガを円滑にスタートするためには、順序立てて必要な工程を踏んでいくことが大切です。
場当たり的に配信を始めてしまうと、読者の興味を引けなかったり、法的リスクを知らないまま配信してしまったりと、不要なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで、ここからはメルマガ運用を始める際に押さえておきたい「9つのステップ」を紹介します。
メルマガ配信の目的・目標を決める
メルマガを始めるとき、最初に行いたいのが「なぜメルマガを活用するのか」を再確認することです。
一般的にメルマガの目的としては、以下が挙げられます。
- 売上アップ(ECサイトやオンラインサービス)
- 新規リストの獲得・見込み客の育成
- イベント集客・セミナー告知
- ブランド認知度向上・ファン育成
- 既存顧客とのリレーション強化
このとき、具体的な「数値」や「指標」に落とし込むと良いでしょう。
- 3か月以内にメルマガ経由の売上を「全体の15%」まで引き上げる
- 半年以内にメルマガ登録者数を「1,000名」に増やす
- 次のオンラインセミナーに、メルマガ経由で「100名」の参加申し込みを獲得する
- 1年かけて、自社ブランドを知る読者を月間1,000人ずつ増や
- リピート率を「20%から25%」へ引き上げる
漠然と「読者とのコミュニケーションに役立てたい」と考えているだけだと、いつまで経ってもメルマガの成果を判断できません。
上記のように目的・目標をしたとき、どのような施策をしていくのか、具体例を挙げてみます。
「3か月以内にメルマガ経由の売上を全体の15%まで引き上げる」
- 配信内容は新商品の紹介や割引クーポンの提供が中心となりがち
- 購入者の声や使用事例などを織り交ぜるとよい
- 開封率やクリック率を継続的に追う
「半年以内にメルマガ登録者数を1,000名に増やす」
- SNSやブログ、セミナーなどでメルマガ登録フォームをアピールする
- 登録後のステップメールを活用する
「次のオンラインセミナーに、メルマガ経由で100名の参加申し込みを獲得する」
- 登壇者の魅力やトピックの面白さを事前に記事や動画で紹介する
- 申込フォームへの誘導リンクのクリック率を上げる
- 読者の疑問に答えるようなQ&A形式の案内を作成する
「1年かけて、自社ブランドを知る読者を月間1,000人ずつ増やす」
- オウンドメディアの更新情報や商品の裏話、運営者のストーリーなどを発信する
- 「この会社だからこそ応援したい」と思ってもらえるような親近感を醸成する
「リピート率を20%から25%へ引き上げる」
- アップセルや定期購入、保守サポート情報などをタイムリーに届ける
- フォローアップメールやアフターケアの案内を定期配信する
メルマガの目的や目標が明確になったら、次にターゲットを設定しましょう。
メルマガのターゲットを明確にする
メルマガ配信においても「ターゲット(あるいはペルソナ)」を設定することは、とても重要な作業です。
以下の項目を中心に、ターゲット設定をしましょう。
- 性別
- 年齢
- 仕事
- 趣味
- 生活リズム など
配信する相手(メルマガ読者)を明確にしておかないと、メルマガの内容がぼやけたり、配信頻度を間違えたりしやすくなります。
「20代後半のキャリアアップに関心の高い女性」「飲食店の開業を目指す30代の男性」など、できるだけ具体的な姿を描くのが理想です。
以下で、ターゲットとその施策について一例を紹介します。
「20代~30代の女性会社員で、休日にアクティビティを楽しみたい層」
- メルマガのデザインやトーンを若々しく、気軽に読みやすい文章にまとめる
- 日常のちょっとした楽しみやライフハックを紹介する
「店舗の集客に課題を抱えている中小企業の経営者」
- 店舗向けのマーケティング方法や具体的事例を定期的に配信する
- 数字を示しつつ実際の成功事例を細かく解説する
「DIYや手芸、モノ作りが好きな30~40代の方」
- 新しい工作アイデアや活用できる素材情報などを発信する
- 「あなたもこんな作品を作れます」などの具体例を提示する
このように、設定したターゲットによって、配信する内容は大きく変わります。
ここからは、メルマガの実務に関することを解説していきます。
メルマガ関連の法律を確認する
法律の順守は、メルマガ運用において避けては通れない要素です。
特に「特定電子メール法」は、不要なメールの大量送信(いわゆるスパム行為)を取り締まる法律として知られています。
配信リストの取得・管理方法や、配信停止の仕組みなどをきちんと満たさないと、罰則の対象となる場合があるため十分注意が必要です。
また、読者のメールアドレスや氏名などを扱うなら「個人情報保護法」にも配慮する必要があります。
| 特定電子メール法 | 個人情報保護法 |
| いわゆる「迷惑メール」を規制することを目的としており メールの送信対象、送信時のルールなどを定めている | 個人情報を取り扱うすべての企業や団体に対して 「個人情報」の取扱に関するルールを定めている |
|
|
※横スクロールで全部見れます
特定電子メール法で押さえておくべきポイントの具体策として、以下を必ず実施しましょう。
- 配信許可(オプトイン)の取得:読者が自主的に登録する仕組みを設け、本人の同意なく一方的に送信しない
- 配信停止の手続きを明示:配信停止リンクをメール本文内に分かりやすく掲載する
- 送信者情報の明確化:発行元の名称や住所、問い合わせ先などを明記する
また、読者リストに含まれる「個人情報」は適切に管理しなければなりません。
特に、リストを第三者に勝手に譲渡・売買するのは論外です。もし本人からの要請があれば、登録情報の開示や削除にも応じる必要があります。
安全な管理体制を維持するために、セキュリティ対策やプライバシーポリシーの策定も欠かせません。
そのため、以下のような5つのルールを守ってメルマガを配信しましょう。
- 個人情報を流出させない
- 個人情報を第三者に開示しない
- メルマガ登録には事前の承諾が必要
- 送信者情報・お問いわせ・解除方法の明記
- 同意記録の保存
法律やルールを守るための具体的な施策については、本サイトの別記事(法律やルールを守ってメルマガを配信する方法)で詳しく解説しています。
また「メルマガ配信スタンド」を使えば、これらの法律もしっかり守りつつメルマガ配信できます。
[char no=”2″ char=”トール”]このような観点からも「メルマガ配信スタンド」は運営者必須のツールです![/char]
メルマガ配信スタンドを選ぶ
メルマガの運用に「メルマガ配信スタンド」は欠かせません。
メルマガ配信スタンドとは、メルマガ配信に必要不可欠な機能を備えたツールです。
- 主な機能:配信リストの管理、開封率の解析、ステップメール配信など
- 費用:月額3,000円〜10,000円(一般的なツール)
また、メルマガ配信スタンドには「無料で使えるプラン」が用意されているケースもあります。
しかし、無料で利用する場合には注意が必要です。
| 無料ツール | 有料ツール |
|
|
メルマガ配信スタンドを選ぶ際には、最低限以下のポイントはチェックするようにしましょう。
- 配信数やリスト数の上限
- テンプレート
- ステップメール機能
- 操作性
- サポート体制
わたしの経験も踏まえながら、こちらの「メルマガ配信スタンドおすすめ10選+配信スタンドの選び方」で、コスパが良い配信スタンドを紹介しています。
[char no=”2″ char=”トール”]個人的には「マイスピー」が一番のおすすめです![/char]
- わたしは、クレジットカード決済機能を使いたかったので「マイスピー」という配信スタンドに落ち着きました
- マイスピーについては『マイスピーを使っている感想』で詳細をレビューしています
メルマガの読者リストを作る・増やす
メルマガ運用において「読者リスト」は、とても貴重な資産です。
メルマガを始めた段階では「既存顧客」や「取引先」など、すでに接点のある方々のデータをもとに、少しずつリストを構築しましょう。
- 既存顧客のデータ
- 名刺交換した会社や担当者のデータ
- イベント参加者のデータ
ここから徐々に「新規の見込み客」を取り入れて拡大していけば、配信の幅が広がり、売上や認知度アップにつながります。
ただし、数を増やすだけではなく、質の高い読者を得ることが重要です。
売り上げや利益につなががる読者を集めるには、以下の方法があります。
- ウェブサイトやSNSに登録フォームを設置する
- 有料広告を活用して専用ページに誘導する
- 展示会やセミナーなどで登録してもらう
これら以外の方法も、メルマガ読者の増やし方7つのポイントで解説してます。
また、効率よくメルマガ読者を増やしていくために「メルマガ登録専用ページ(オプトインページ)」を作りましょう。
オプトインページには、以下のような特徴やメリットがあります。
- メルマガ登録専用のページ
- メルマガの主旨や目的を伝えられる
- メルマガを読むメリットを伝えられる
- 登録時の注意事項などを伝えられる
- 特典やプレゼントを紹介できる etc
オプトインページでは「どんなメルマガなのか」とか「メルマガで何が得られるのか」など、配信するメルマガについてアピールをすると良いです。
オプトインページの作り方には6つのコツがあるので、これらを取り入れながら作りましょう。
[char no=”2″ char=”トール”]オプトインページは「何度も作り直しながら」完成形に近づけていきましょう![/char]
メルマガを作成する
メルマガを作成する段階では、件名やタイトルの付け方から、本文の構成、さらにはテキストメールにするかHTMLメールにするかなど、いくつかのポイントを検討する必要があります。
これらを工夫することで、開封率や読みやすさを大きく変えられるため、目的やターゲット像を踏まえて最適な形を模索しましょう。
まず、受信トレイに並んだたくさんのメールの中から、あなたのメルマガを開封してもらうためには、以下のように「件名の工夫」が欠かせません。
- 限定感や数字を盛り込む:「【3日限定】新作アイテム特別セール」など、緊急性を訴求する
- 読者の悩み・興味を直接刺激する:「忙しい人向け!5分で読める時短レシピ特集」など、具体的なメリットを伝える
- ブランド独自の視点を出す:「○○編集部が見つけた最新テクニック」など、読み手が得られる新しさや価値を打ち出す。
これらの他にも、メルマガの開封率をアップする方法はいくつもあるので、色々と試してみてください。
次に、メルマガを書くポイントは「短く分かりやすく」が原則です。
その他にも、以下に挙げた「メルマガを書くときのコツ」を参考にするとよいでしょう。
- 結論から書く
- 文字数を意識
- 目的を決める
- 経験談や実績
- 余白とか改行
- 押し売り厳禁
これらの詳細について、メルマガが上手く書ける「6つのコツ」で解説しました。あわせてご覧ください。
また、メルマガの作成に慣れてきたら「テキストメール」と「HTMLメール」の使い分けも視野に入れてみましょう。
| テキストメール | HTMLメール |
|
|
※横スクロールで全部見れます
これら両方を使い分けたり、A/Bテストで効果を検証したりすることで、自社(個人)の読者層にとって最適なスタイルを見極めていくのが得策です。
[char no=”2″ char=”トール”]最初は、上手に書こうとせずに「読者が知りたいこと」にフォーカスしましょう![/char]
メルマガの配信頻度・スケジュールを決める
メルマガの配信頻度は、読者が負担に感じるか、それとも役立つ情報源と感じてくれるか、を左右する重要なポイントです。
配信のし過ぎは「しつこい」と思われやすく、逆に間隔が空きすぎると「忘れられてしまう」可能性があります。
ターゲット層の「ライフスタイル」や「目的」に合ったタイミングを見極めましょう。
- 主婦層がターゲットなら、朝の家事が落ち着く時間帯や子どもの送迎後などが狙い目
- ビジネスマン向けなら平日昼の休憩時間や、帰宅後の夜間帯に開封率が高まることが多い
こうした生活リズムを踏まえ、配信時間帯を試行錯誤すると反応率が向上しやすくなります。
また、配信するタイミングとともに「配信する頻度」も決めておきます。以下も参考にしてください。
| 頻度 | 特徴 |
| 週1回程度 |
|
| 月2回程度 |
|
| 毎日配信 |
|
※横スクロールで全部見れます
メルマガ配信頻度は目的に合わせて変えるのが理想です。そして、メルマガを配信する頻度・内容などによって、運用リソースは変わります。
複数のメンバーがメルマガ作りに関わる場合、役割分担が曖昧だと混乱しやすいため、作成担当、チェック担当、配信担当など分け、全体のスケジュールを可視化すると良いです。
特に、キャンペーン時期などは直前に慌てないよう、余裕を持ったスケジュール設定を心がけましょう。
メルマガ配信に効果測定をする
メルマガは「配信して終わり」ではありません。
配信後には「効果測定」を行い、得られたデータをもとに次回以降の配信内容を改善していくことが、成果を積み上げるコツです。
たとえば、件名のちょっとした変更で開封率が大きく変わる場合もあるので、検証を繰り返し行いましょう。
| 測定する指標 | 内容 |
| 開封率 |
|
| クリック率 |
|
| CVR(コンバージョン率) |
|
※横スクロールで全部見れます
A/Bテストを行いつつ効果測定をすれば、より正確に施策効果を把握できるでしょう。
A/Bテストをする際は「件名のみ」や「配信時間のみ」といった形で、少しづつテストをしていくのが理想です。
また、読者リストの「メンテナンス」と「クリーニング」をすることも、正しい効果測定をするために欠かせません。
- 長期間開封されていないアドレス
- エラーメールが続くアドレス
こういったアドレスは定期的にリストから除外しないと、配信コストを無駄にしてしまいます。
しかも、リストに古いアドレスが多いと、送信元IPの評価が下がり、迷惑メールフォルダに振り分けられる可能性も高まります。
最低でも半年に一度程度はリストをチェックし、適宜クリーニングする習慣をつけましょう。
メルマガを軸に施策を広げる
メルマガは単独でも成果を出せますが、さらに「さまざまなマーケティング施策と連動する」ことで相乗効果を発揮します。
たとえば、以下の連動方法があります。
- 他チャンネルとの連携で相乗効果を狙う
- ブランド戦略としてメルマガを活用する
- ステップメール・MAツール連携で自動化を進める
では、それぞれを詳しく見ていきましょう。
他チャンネルとの連携で相乗効果を狙う
SNSやブログ、YouTubeチャンネルなどと連携すると、読者を多角的にフォローできるメリットがあります。
メルマガで告知してSNSでシェアを促し、さらに動画で製品デモを見せるといった具合に、複数の接点を作ると定着率が上がりやすいです。
特に商品の購入前後で異なるコンテンツを提供すれば、リピート購入や口コミも期待できるでしょう。
ブランド戦略としてメルマガを活用する
定期的な配信を通じて、企業やブランドのストーリーや価値観を読者に伝えることができます。
新商品の開発裏話やスタッフのこだわりなど、SNSでは流せない深い内容をメルマガで配信することで、読者がブランドに愛着を持ちやすくなるでしょう。
特に、リピーターやファンを育成したい場合は、メルマガを「特別な情報を得られる場」と位置付けるのが効果的です。
ステップメール・MAツール連携で自動化を進める
見込み客の行動や属性に合わせて、自動的に最適なメールを送れる仕組みとして「ステップメール」や「マーケティングオートメーション(MA)ツール」の活用が挙げられます。
たとえば、初回登録時にはウェルカムメールを送り、数日後に商品紹介メール、さらに反応が良ければ購入特典メールを配信するといった流れをあらかじめ設定しておけば、運用の手間を減らしながら確度の高いフォローを継続できます。
導入にはコストや知識が必要な場合が多いですが、長期的に見ると高いROI(投資対効果)を期待できるでしょう。
今すぐ取りかかれる具体的アクション
まずは、小さな一歩からスタートし、失敗や改善を重ねながら自社や自身のビジネスに最適化していきましょう。
たとえば、目標を「メルマガ経由の問い合わせ件数を月20件にする」といった形で数値化してみます。
もし目標を達成できなくても、以下のように修正を繰り返すことでPDCAを回せます。
- ターゲットを詳細に絞る
- 文章のトーン&マナーを変える
- 配信頻度や曜日、時間帯を見直す
- 競合調査を再度行う
- 件名やコンテンツを再設計する
また、すぐ手を付けられる具体的アクションを表にまとめました。
| アクション項目 | 内容例 |
| ゴール設定 | 「3か月後までにCVRを5%に引き上げる」など明確な数値を決定 |
| 配信ツールの比較検討 | 無料・有料を含め複数ツールを試用し、機能とコストを比較 |
| 法的要件のチェック | 特定電子メール法・個人情報保護法の概要を再確認 |
| 読者リストを作る | 既存顧客、名刺、セミナー参加リストなどからリストを作成 |
| コンテンツテンプレートの作成 | 件名・導入文・本文構成など、ひな形を用意して負担を軽減 |
| 初回配信とデータ検証 | 開封率・クリック率を計測し、次回配信に向けて調整 |
| リストの定期メンテナンス | 未開封が続くアドレスやエラーアドレスを整理・クリーニング |
| 他チャネル連携 | SNSやブログ、YouTubeへ誘導し、多面的なコミュニケーションを図る |
※横スクロールで全部見れます
このように、一連のアクションを計画的に行うことで、メルマガ運用が単なる「メール送信」から「ビジネス成長のエンジン」へと変わっていくはずです。
小さな成功体験を積み重ねながら、ビジネスや活動に役立つメルマガを構築していきましょう。
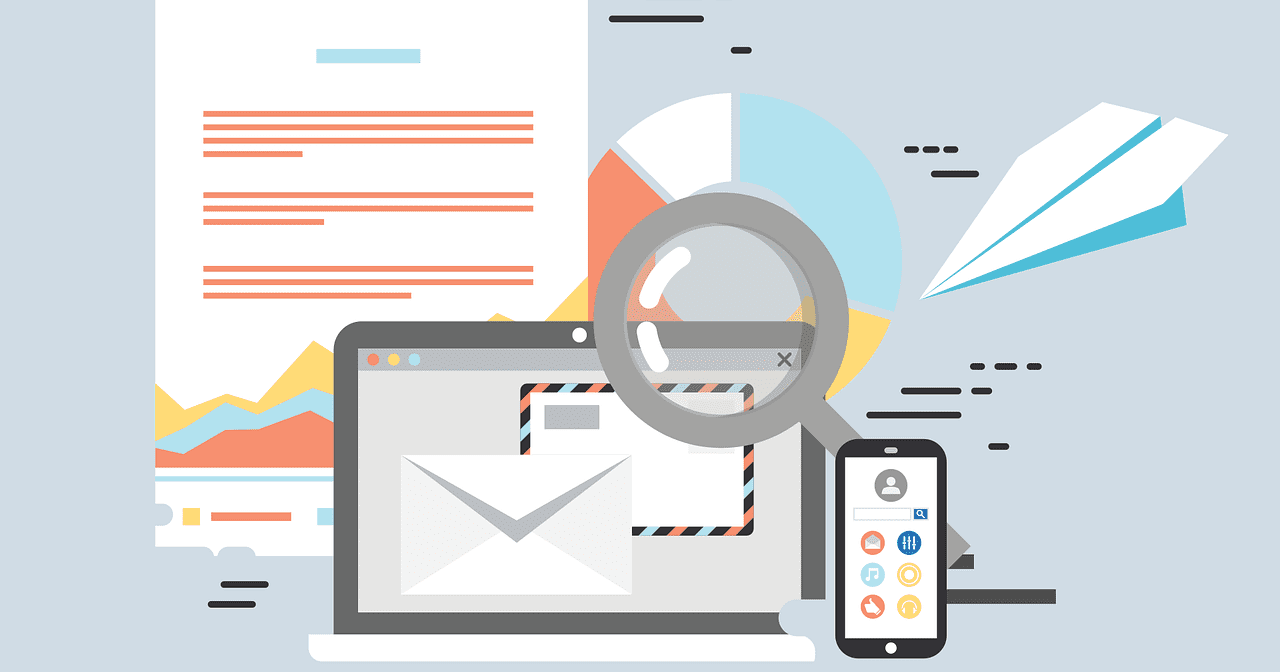

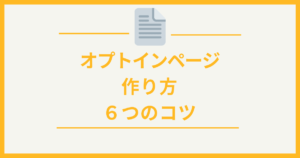
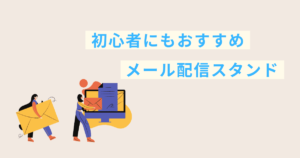
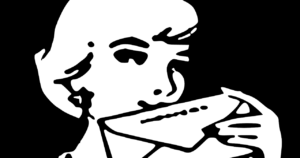


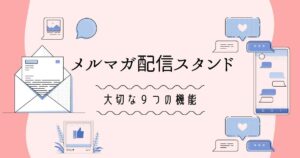

コメント