- メルマガの基礎知識と役割を押さえ、効果的な運用法を理解できる
読まれるメルマガの書き方15のコツ(件名や導入文、PREP法、CTAなど)を網羅的に習得できる
セグメント配信やABテストなど開封率・クリック率を上げる配信・運用のコツがわかる
テンプレートやチェックリスト、件名例といった実践に役立つ付録つきで、記事を読み終えたらすぐ行動に移せる
[char no=”1″ char=”トール”]今回のテーマは『メルマガの書き方・運用のコツ』について![/char]
どうもー!トールです(@tooru_medemi)
メルマガを配信しても「なかなか開封されない」「最後まで読まれない」ことは、初心者などによくあるケースです。
しかし、メルマガの書き方や運用のコツを覚えないと、いつまで経っても読まれないメルマガを配信し続けてしまいます。
そこで本記事では、わたし自身の失敗と成功の実体験を交え、初心者でも今日から実践できる具体的なメルマガのコツを解説します。
メルマガの基礎
まずは、メルマガの基本をおさらいしましょう。
メルマガ(メールマガジン)とは、登録した読者に対して定期的にメールで情報を届けるマーケティング手法です。
ブログやSNSとは異なり、一度獲得したリストに繰り返しアプローチできるのが大きな特徴です。
- 企業からのニュースレター
- ECサイトの商品案内
- 個人事業主のノウハウ配信 など
メルマガの形態はさまざまですが、共通する役割は「見込み客やファンとの関係構築」と「利益の創出」です。
メルマガが持つ強み
メルマガは古典的な手法に見えますが、その効果は現代でも健在です。
事実、メールマーケティングの「平均ROI(投資対効果)は4,400%」にも達し、デジタルマーケティングチャネルの中で最も費用対効果が高い手段の一つとされています。
また、メルマガは読者と直接コミュニケーションが取れる点も強みです。
読者のメールボックスにダイレクトに届けられるため、情報到達率が高く、公式SNSやブログよりも読者にしっかり情報を届けられます。
開封率・クリック率など重要指標
メルマガの効果を語る上で外せないのが「開封率」と「クリック率」です。
開封率とは「配信したメールのうち何%が開封されたか」を示し、クリック率は「開封されたメール内のリンクが何%クリックされたか」を示す指標です。
- 業種や業態によって差がある
- メルマガの平均開封率は15~25%
- 平均クリック率は2~3%
開封率が低ければ件名や配信時間に課題があり、クリック率が低ければ本文内容やリンクの配置に改善の余地ありと判断できます。
わたし自身のメルマガでは、登録読者1,000人規模ですが「開封率50~60%」を維持できています。
これは平均を大きく上回る数値です。これを実現しているノウハウを15個に分けて紹介します。
読まれるメルマガを書くための15のコツ
メルマガは書き方を少し工夫するだけで、読者の反応が大きく変わります。
ここでは件名や導入文、文章術から心理テクニックまで、筆者も実践して効果を実感した15個のコツを紹介します。
| 項目(コツ) | 特徴(ポイント) |
|---|---|
| 1. ターゲット読者を明確にする | ・誰に向けて書くのかを明確化する ・読者が求める情報や適切な語り口が定まり、反応率アップにつながる |
| 2. メルマガの目的とテーマを1つに絞る | ・1通に複数の要素を詰め込みすぎない ・「販売促進」「ノウハウ提供」など目的を1つに定め、読者が何を得られるかを明確に伝える |
| 3. 読者を引きつける件名をつける | ・件名が開封率を大きく左右する ・20~40文字以内で前半にキーワードや数字を入れ、読者の興味を刺激する表現にする |
| 4. 差出人名で安心感と統一感を与える | ・「誰からのメールか」を一目でわかる名前に設定し毎回統一する。 ・「人名+屋号」などで親近感を演出し、迷惑メールの疑いを避ける |
| 5. プレヘッダーテキストを活用する | ・件名の後に表示される短い文を第二の件名として使い、補足情報や魅力を伝える ・開封率アップに有効 |
| 6. 導入文で読者の興味と共感を引く | ・冒頭で短い挨拶・共感ポイントを示し、「自分のための内容だ」と思わせる ・長すぎると離脱率が上がるので、簡潔に |
| 7. 結論を先に伝えてから詳細を書く | ・忙しい読者に配慮し「結論ファースト」で伝える ・「結論→理由→事例→再結論」の流れを意識すると要点が分かりやすい |
| 8. PREP法など文章テンプレートを活用する | ・Point(結論)→Reason(理由)→Example(事例)→Point(再結論)の型で論理的に整理 ・文章作成が苦手な方はテンプレートに当てはめると書きやすい |
| 9. 本文は短く簡潔に(3分以内で読める長さ) | ・冗長な長文は敬遠される ・1分約500文字の目安で1,500文字程度を心がけ、詳細はリンクで補足するなど工夫 |
| 10. 箇条書き・番号・記号を使って要点を強調 | ・ダラダラと文を続けず、箇条書きや番号リストを活用 ・読者が見出しや重要ポイントを瞬時に把握できるよう視覚的に整理 |
| 11. 余白や改行を活用してスマホでも読みやすく | ・1段落は50文字前後で改行し、段落間に1行空ける ・狭い画面でもストレスなく読めるレイアウトを整え、最後まで読ませる |
| 12. 経験談や事例を盛り込んで信頼性を高める | ・失敗談や成功事例など実体験を出すとオリジナリティと信頼度が向上 ・具体的データやエピソードは説得力を増す |
| 13. 読者に語りかける一人称で親近感を出す | ・「あなた」「~ですよね?」など二人称表現を使い、一対一で話しかける雰囲気を演出 ・法人でも可能な範囲でキャラクターを出す |
| 14. 押し売りはせず価値提供を優先する | ・8割は有益情報、2割が販売促進のバランスを意識 ・しつこいセールスは敬遠されるため、あくまで自然に商品・サービスを紹介 |
| 15. 明確なCTA(行動喚起)で次のアクションを促す | ・「資料請求」「購入」「SNSフォロー」など1つに絞った行動を促す ・本文や末尾でわかりやすいリンクやボタンを用意し、迷わずクリックしてもらう |
※横スクロールで全部見れます
どれも今日から使える実践的なヒントばかりですので、ぜひお手元のメルマガに取り入れてみてください。
これらのコツについて、ここから詳しく解説します。
ターゲット読者を明確にする
まず「誰に向けて書くのか」をハッキリさせましょう。
メルマガの内容は、漠然と不特定多数に届けるよりも「特定のペルソナ(読者像)」を意識した方が深く刺さります。
以下のように、ターゲットはできるだけ具体的に想定しましょう。
- 30代女性の副業初心者向け
- 中小企業の経営者向け
ターゲットが明確になると「読者が求める情報」や「適切な語り口」が見えてきます。
誰に届けたいメッセージなのかを明確にすることが、読まれるメルマガの第一歩です。
AIを使ってメルマガを書くときも、ターゲットを明確に設定してから指示を出すと、より質の高い文章が作れます。
メルマガの目的とテーマを1つに絞る
1通のメルマガで「伝えたいことは1つ」に絞るのが鉄則です。
あれもこれもと盛り込むと焦点がぼやけ、結局何を伝えたいのかが読者に伝わりません。
配信前に「今回のメルマガの目的は何か?」を自問し、以下のように目的を定めましょう。
- 商品・サービスの告知・販売
- 読者に有益なノウハウ提供
- 自社(自分)のブランディング強化
- イベントやキャンペーンの案内 など
例えば「ノウハウ提供」が目的ならノウハウだけを書く、「商品紹介」が目的なら商品の価値を伝えることに徹します。
「1メルマガ=1目的」を意識することで内容に一貫性が生まれ、読者にメッセージが明確に伝わります。
読者を引きつける件名をつける
メルマガの件名(タイトル)は、開封率を左右する最重要ポイントです。
読者は受信トレイにずらりと並ぶメールの中から「件名」を見て開封判断をします。読まれるメルマガにするには、件名でいかに興味を引けるかが勝負です。
以下のポイントを意識してみましょう。
- 20~40文字以内に収める(長すぎると後半が切れる)
- 前半15文字に伝えたいキーワードや魅力的な要素を入れる
- 数字や具体的な言葉を使ってインパクトを与える(例:「3日で結果が出る」「売上200%アップ」)
- 読者のメリットやベネフィットを示す(例:「○○の方法」より「○○の方法【無料テンプレート付】」)
- 必要に応じて【期間限定】や【お知らせ】などカテゴリを示すキーワードを括弧書きで入れる
▼件名の良い例・悪い例
| 悪い例 | 良い例 |
| メルマガ10月号のお知らせ | 【10月限定】初心者向けメルマガの書き方セミナー開催! |
| 新商品が出ました。買ってください | たった5分で効果◎:新商品〇〇の使い方とお得情報 |
| (無題) | 【無料テンプレート有】メルマガ反応率アップ5つの秘訣 |
※横スクロールで全部見れます
上記のように、「何となく平凡な件名」ではなく「読者が思わず開きたくなる件名」を工夫しましょう。
ポイントは「具体性」と「読者視点の魅力」です。
「自分だったらこのタイトルを開封するか?」と客観視しながらアイデアを練ってみてください。
差出人名で安心感と統一感を与える
件名と並んで見られる「差出人名(送信者名)」も、メルマガ配信では大切な部分です。
差出人名が信用できないと感じれば、中身に関係なくスルーされたり迷惑メール扱いされる可能性もあります。
基本は「誰からのメールか一目でわかる名称」にし、できるだけ毎回統一しましょう。
- 個人名で認知されているなら「〇〇(自分の名前)」
- 企業で認知されているなら「△△株式会社 メルマガ担当」
毎回表記がバラバラだと「いつものあのメルマガだ」と読者が気付けないため、統一することが信頼感・安心感につながります。
差出人名は地味ながら開封率アップの裏方とも言える場所なので、最適な名前を設定しましょう。
プレヘッダーテキストを活用する
プレヘッダーテキストとは、受信ボックス上で件名の後に薄い文字で表示される文章のことです(メール本文の冒頭部分が表示されることもあります)。
件名だけでは伝えきれない「補足情報」や「興味を引く一言」をプレヘッダーに仕込むことで、開封率向上を狙えます。
例えば「件名:【無料セミナー】応募者急増中!」に対し、プレヘッダーで「※残席わずか。詳細はこちらから→」と入れるイメージです。
[char no=”2″ char=”トール”]件名の次に表示されるため「第二の件名」とも言えます![/char]
設定方法は、メール配信システム上でプレヘッダー用のテキスト入力欄がある場合がほとんどです。
もし自前でHTMLメールを組むなら、メール本文の最上部に「<span style="display:none;">この部分がプレヘッダーになります</span>」のように記載してもOKです。
少しの手間をかけるだけで、開封率に差が出るポイントなので、ぜひ活用してみてください。
導入文(あいさつ文)で読者の興味と共感を引く
読者がメールを開封して真っ先に目にするのが「導入文(リード文)」です。
いきなり本題に入る前に、導入部分で短い挨拶や前置きを入れて読者の心をつかみましょう。
以下は、導入文に使えるアイデアの一例です。
| 施策例 | ポイント |
| 季節の挨拶や時事ネタ |
|
| 読者の名前を差し込み |
|
| 共感や悩みへの言及 |
|
※横スクロールで全部見れます
ただし、導入文が長すぎるのは禁物です。あくまで数行~短い段落1つ程度にとどめ、早めに本題(本文)に入るようにしましょう。
導入文は「つかみ」の部分です。ここで共感や興味を引ければ、本文を読んでもらえる可能性がグッと高まります。
結論を先に伝えてから詳細を書く
メルマガ本文を書き始める際は、まず「結論」を冒頭に持ってくることを意識しましょう。
これはビジネス文章の基本原則でもありますが、忙しい読者に配慮し最初に要点やメリットを伝えることが大切です。
「結論→理由→具体例→再結論」という流れを意識すると、話が分かりやすくコンパクトにまとまります。
[char no=”2″ char=”トール”]例えば「伝えたい結論」を冒頭で宣言し、その後に「理由」や「詳細な説明」を書いていくイメージです![/char]
こうすることで、冒頭部分で読者の関心を捉え、離脱を防ぐ効果があります。
逆に、結論が見えないまま前置きや説明が延々続くと、「何が言いたいの?」と飽きられて最後まで読まれません。
この文章の書き方に慣れるまでは、テンプレートの力を借りるのも手です。次のコツで紹介する「PREP法」は、その代表格と言えるフレームワークになります。
PREP法など文章テンプレートを活用する
「PREP法」とは、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再結論)の頭文字を取った文章の書き方です。
論理的で分かりやすい文章を書く基本型として、ビジネス文書やブログ記事でも広く使われています。
メルマガ執筆に慣れないうちは、このPREP法に沿って文章を組み立てると失敗が少ないです。
- Point(結論):まず言いたい結論・要点をシンプルに述べる
- Reason(理由):その結論を支える理由や背景を説明する
- Example(例):理由を裏付ける具体的な事例やデータを示す
- Point(結論):改めて結論を簡潔にまとめ、読者へのメッセージとして締める
例えば「メルマガには結論ファーストが重要だ」という主張を伝えたい場合、以下の流れになります。
結論:メルマガを書くときは最初に結論を書くべきです。
理由:なぜなら、忙しい読者は冒頭部分で読むか離脱するかを判断するからです。
具体例:実際、筆者の配信リストでも結論を冒頭に書いたメルマガは開封後5秒以内の離脱率が下がりました。
再結論:以上の理由から、最後まで読まれるメルマガを書くには冒頭で結論を述べることが有効です。
PREP法以外にも「QUEST法」「SDS法」など文章テンプレートはありますが、まずは汎用性の高いPREP法がおすすめです。
型を使うことで文章全体が整理され、結果として短く分かりやすいメルマガになります。
▼あわせて読みたい
PREP法のメリットや具体例について
本文は短く簡潔に(3分以内で読める長さ)
忙しい現代人に長文のメールを読ませるのは至難の業です。メルマガはサクッと読める長さを心掛けましょう。
「ちょっとした隙間時間に読める」くらいが理想で、その目安は「約3分」以内です。
一般的な日本語文章の読了速度は、1分あたり約400~600文字と言われます。これを目安に文字数を考えみましょう。
[char no=”2″ char=”トール”]わたしは「1分500文字」ほどを目安に、合計1,500文字前後で書くことが多いです![/char]
これなら3分弱で読み終えられ、スマホでスクロールしても長すぎずちょうど良いボリュームです。
どうしても伝えきれない情報がある場合は、リンクを活用する手もあります。
詳細な説明記事へのURLや参考動画(YouTube等)へのリンクを本文に入れ、「興味がある人は続きをどうぞ」と誘導すれば、メルマガ自体は短く保ったまま深い情報提供も可能です。
ポイントは、冗長な表現や重複を省いて簡潔に書くこと。後述するチェックリストでも触れますが、配信前に声に出して読んでみて冗長な部分がないか確認するのも有効です。
箇条書き・番号・記号を使って要点を強調
文章が長く続くと、どうしても読み飛ばされたり理解が曖昧になったりします。
箇条書きや番号付きリスト、ダッシュ(-)や矢印(→)などの記号を活用して、読者の目を引きつつ要点を整理しましょう。
例えば、メリットを列挙する場合、「第一に~。第二に~。第三に~。」とダラダラ書くより、以下のように箇条書きにすると格段に読みやすくなります。
- 第一のメリット:○○が向上する
- 第二のメリット:□□を削減できる
- 第三のメリット:△△が簡単になる
このように、視覚的に情報が整理されると、読者は重要ポイントを瞬時に把握できます。
また、数字を使うこと自体が情報の具体性・信頼性を高める効果もあります。「多数の方が成功しています」より「92%のユーザーが効果を実感」の方が説得力が増すのはそのためです。
メルマガでは長い段落が続かないよう、小見出しや箇条書きを適宜挟んでリズムよく伝えましょう。
読者は画面をサッとスクロールしながらポイントを追っていくので、視覚的な手がかりがあると親切です。
余白や改行を活用してスマホでも読みやすく
「読まれるメルマガ=読みやすいメルマガ」です。
もちろん読みやすい文章を書くスキルは大切ですが、それだけでなくレイアウトの工夫でも読みやすさは向上します。
特に意識したいのが「余白(空行)」や「改行」の使い方です。
1段落(ブロック)は50文字以内に収める。長くても3~4行で改行する
段落間に1行程度の空白行を入れ、文章が詰まりすぎないようにする
箇条書きや「( )」「「」」といった記号も適度に使い、文章にリズムと余裕を持たせる
このようなレイアウト上の工夫は、特にスマートフォンで読むユーザーに効果的です。
スマホの小さい画面では、びっしり詰まった長文は圧迫感があり読む気をなくしてしまいます。
逆に、適度に改行や空白がある文章は、それだけで「なんだか読みやすそう」という印象を与えられます。
見た目の読みやすさも読了率に直結しますので、ぜひレイアウトにも気を配ってみてください。
経験談や事例を盛り込んで信頼性を高める
メルマガの読者は「この人の話は本当だろうか?」と無意識に考えています。
そこで有効なのが、自分の「経験談」や具体的な「成功・失敗事例」を盛り込むことです。
実体験に基づく話はオリジナリティがあり、他のどこにもないあなただけのコンテンツになります。
[char no=”2″ char=”トール”]実体験は「読者との信頼関係」を築くことにも役立ちます![/char]
他にも「実績データ」や「肩書き」を本文中で触れるのも有効です。
例えば「創業5年で累計1万人に配信したノウハウです」「〇〇認定コンサルタントが教える~」といった一文があるだけで、専門性や信頼性がぐっと上がります。
自慢になりすぎない程度に、自分だけが提供できるエピソードや情報を出し惜しみしないようにしましょう。
読者に語りかける一人称で親近感を出す
メルマガは基本的に「一対多」のコミュニケーションですが、あえて一対一に話しかける口調を意識すると、読者は自分だけに語りかけられているように感じます。
これはコピーライティングでよく言われるテクニックで、読者との心理的距離を縮める効果があります。
親近感を出すために、以下のテクニックも意識してみましょう。
- 「皆さん」よりも「あなた」
- 敬語ばかりだけでなく、時折「〜ですよね?」と語りかける
- 「弊社」より「私」「僕」といった一人称を使う
ただし、企業のメルマガなど書き手のキャラクターを出しにくい場合は、無理に崩す必要はありません。
その場合でも、読む人を想像して語りかけるトーン(例:「この先は重要なポイントです。ぜひ押さえてください」)を入れるだけで違います。
心の中で読者と対話しながら書くイメージで、温かみのある文章を目指しましょう。
押し売りはせず価値提供を優先する
メルマガの目的が商品の宣伝や販売であっても、露骨な押し売りにならないよう注意が必要です。
「今すぐ買ってください!」「○○円ポッキリお得!」といった過剰な売り込みは、多くの読者に嫌われてしまいます。
現在は、強引な広告・セールスに敏感な人が多く、押し売り感があると即配信解除されたり、最悪の場合迷惑メール認定される恐れもあります。
[char no=”2″ char=”トール”]押し売りはダメ!ぜったい![/char]
では、どうすれば売り込み臭を減らせるか?コツは自然な文脈で商品やサービスを紹介することです。
例えば、本文の中でノウハウを語りつつ、その解決策として自社商品を「ちなみに~というサービスがあります」とさらりと触れる、あるいはメルマガの最後(フッター付近)に案内を載せる程度にとどめます。
一通のメールで複数商品の宣伝をしない、一度の配信で執拗に同じ案内を繰り返さない、といった配慮も重要です。
- 流れに沿って自然に商品名を出す
- メルマガの最後で商品を宣伝する
- 1通の中で1つの商品だけを宣伝
- 販売目的のメルマガ頻度を減らす
- キャンペーン情報を一緒に載せる
わたしもメルマガで自身のサービス紹介を行いますが、全体の8割は有益情報、残り2割で関連サービス案内というバランスを心掛けています。
読者からすれば「毎回良い情報をくれる人が紹介するサービスなら見てみよう」という心持ちになり、押し売り感なく興味を持ってもらえます。
価値提供を最優先に考えて信頼を積み上げ、その延長線上で商品紹介を行いましょう。
明確なCTA(行動喚起)で次のアクションを促す
メルマガでは、メールを読んだ読者に「取ってほしい行動(CTA:Call to Action)」を明確に伝えましょう。
せっかく最後まで読んでもらっても、読者が「で、どうすればいいの?」と戸惑っては機会損失です。
メルマガの目的に応じて、読者に起こしてほしい具体的なアクションを一つ決め、それを本文中または末尾でしっかり案内します。
- 商品購入を促す:「▼今すぐ商品詳細をチェックする(URL)」とボタンやリンクを配置
- 資料ダウンロード:「今なら無料のPDF資料をプレゼント中!こちらから入手できます→URL」
- 問い合わせ誘導:「サービスに関するご質問はお気軽にこちらまで(お問い合わせフォームURL)」
- SNSフォロー:「最新情報はTwitterでも配信しています。よければフォローお願いします!→@アカウント」
CTAを入れる位置は、読了後すぐに行動してもらえるよう「メールの最後」が定番ですが、長文の場合は途中にボタンを挟んでも問題ありません。
重要なのは、アクションをひとつに絞ること。あれもこれもとリンクを並べすぎると結局どれもクリックされなくなります。
わたしの経験上、CTA付きリンクのクリック率が思わしくない場合は、リンクのテキストやボタンのデザイン、配置を変えてA/Bテストをすることで改善できました。
読者がスムーズに次のステップへ進めるよう、明確で魅力的なCTAを用意しましょう。
よくある質問とその答え(Q&A)
最後に、メルマガの書き方や運用について寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。疑問点の解消にお役立てください。
Q1. メルマガの開封率が低いと感じます。どうすれば上げられますか?
A1. 開封率向上の鍵はズバリ「件名改善」と「送信リストの質」です。まず件名を見直しましょう。
ただ情報を並べるのではなく、読者の興味を引き感情に訴えるワードを入れてみてください(例:「驚きの」「簡単○秒で」など)。
また、定期的に休眠読者を整理するのも大事です。
開封実績がしばらく無いアドレスに送り続けても開封率の母数が下がるだけなので、思い切ってリストから外すことも検討しましょう。
セグメント配信で興味の近い人にだけ送るようにすれば、開封率は改善しやすくなります。
Q2. 適切なメルマガ配信頻度はどれくらいですか?
A2. 一概には言えませんが、一般的には週1回前後が多い印象です。
情報過多にならない頻度で、読者の記憶に残り続ける間隔が望ましいです。
少なすぎる(月1回以下など)と存在を忘れられ、逆に多すぎる(週3以上)と読む負担が増します。
まずは月2~4回を試し、反応や解除率を見て微調整してください。
配信タイミングも含め、前述の通りA/Bテストで最適値を探るのがおすすめです。
Q3. メルマガの件名に絵文字や記号は使うべきでしょうか?
A3. ケースバイケースです。件名の絵文字は目立つ反面、業種や受け手によっては軽い・スパムっぽい印象を与える可能性もあります。
一般消費者向け(B2C)のカジュアルな内容なら😊や⭐など入れると開封率が上がる例もあります。
一方、B2Bやフォーマルな内容では控えた方が無難です。どう感じるかは読者次第なので、一度少数に配信して反応を見ると良いでしょう。
また、多用はせず1~2個に留める、件名先頭ではなく末尾に付けるなど工夫してください。
記号についても「【】」や「!?」程度なら効果的ですが、$$$や過剰な「!」連打はスパム判定のリスクが高まるので注意が必要です。
Q4. メルマガ初心者ですが、すぐ始めるには何が必要ですか?
A4. メール配信スタンドと配信リスト(読者メールアドレスのリスト)が必要です。
既にお客様のメールリストがあるなら、適切な許諾(オプトイン)が得られているか確認しましょう。
ゼロから集める場合は、Webサイトに登録フォームを設置したり、SNSやイベントで「メルマガ登録すると○○プレゼント」のような誘導施策を行うと効果的です。
配信スタンドは無料から使えるものも多いので、まずはお試しで1つ契約し、自分自身にテスト送信するところから始めてみましょう。
操作に慣れたら、早速簡単な挨拶メールや自己紹介メールを作成して配信してみることをおすすめします。
最初の一通を送るハードルを越えれば、あとはこの記事のコツを1つ1つ取り入れながら改善できます。
Q5. メルマガ配信で注意すべき法律はありますか?
A5. 日本では「特定電子メール法」という法律があります。
営利目的のメールを送る際のルールを定めたもので、以下を守る必要があります。
事前に受信者の同意(オプトイン)を得ること:勝手に営業メールを送りつけてはいけません。登録フォームや名刺交換などで「メール送って良い」と了承を得た人だけに送りましょう。
配信停止(オプトアウト)の手段を提供すること:メール内に「解除はこちら」のリンクや返信で停止できる旨を明記する義務があります。解除依頼があれば速やかに配信を止めましょう
発行者の情報を明記すること:差出人の氏名または法人名、住所、連絡先をメールに記載する必要があります。これはフッターに入れておけばOKです。
これらを怠ると最悪罰則もありますが、常識的な範囲で適切に運用していれば恐れることはありません。
多くのメール配信ツールでテンプレート化されている事項でもありますので、設定画面などを確認し漏れがないようにしましょう。
Q6. AIに任せてメルマガを書けば自動化できますか?
A6. 現状、完全にAI任せで質の高いメルマガを配信し続けるのは難しいでしょう。
AIは便利ですが、読者との細やかな共感や、自社ならではの専門知識、タイムリーな話題提供など、人間の洞察が不可欠な部分があります。
AIが書いた文章は一見もっともらしくても、読み手には無機質に感じたり文脈にそぐわない表現が混じったりすることもあります。
ただし、部分的にAIを活用するのは大いにアリです。
アイデア出しや言い回しの改善、定型文生成などでサポートさせ、人間がそれをチェック・修正して仕上げる流れがおすすめです。
将来的にはAIの精度がさらに上がり、もっと自動化できる可能性もありますが、現時点では「AI + 人間」のハイブリッド執筆がベストといえます。


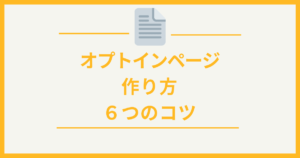
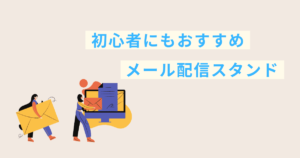

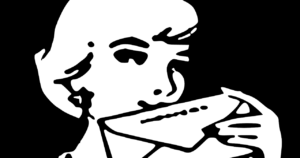


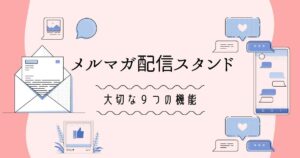
コメント