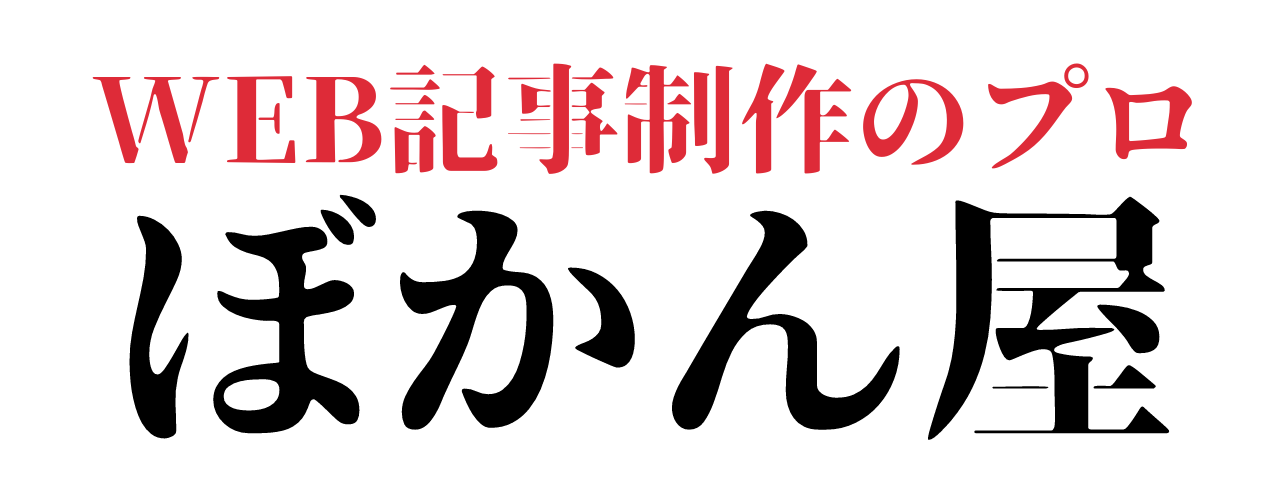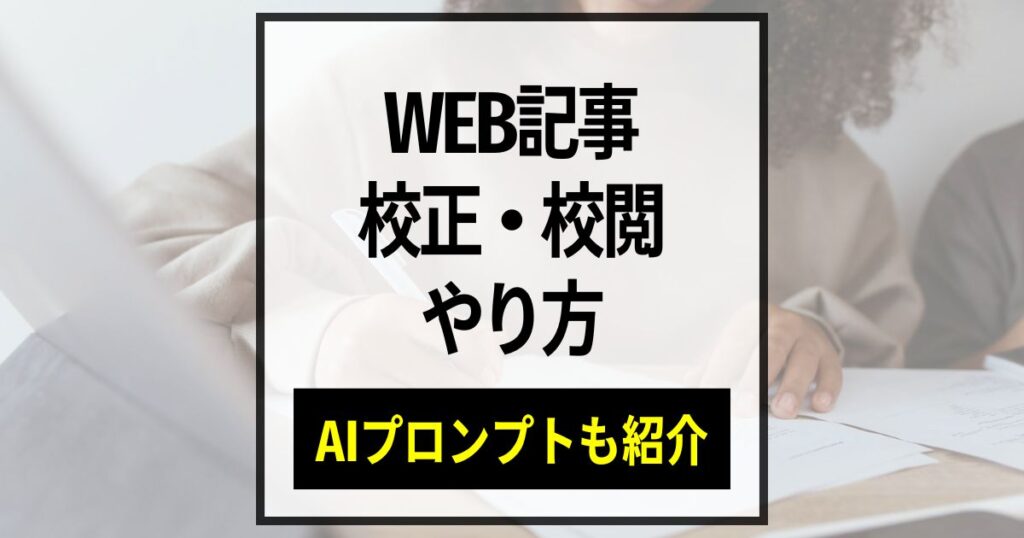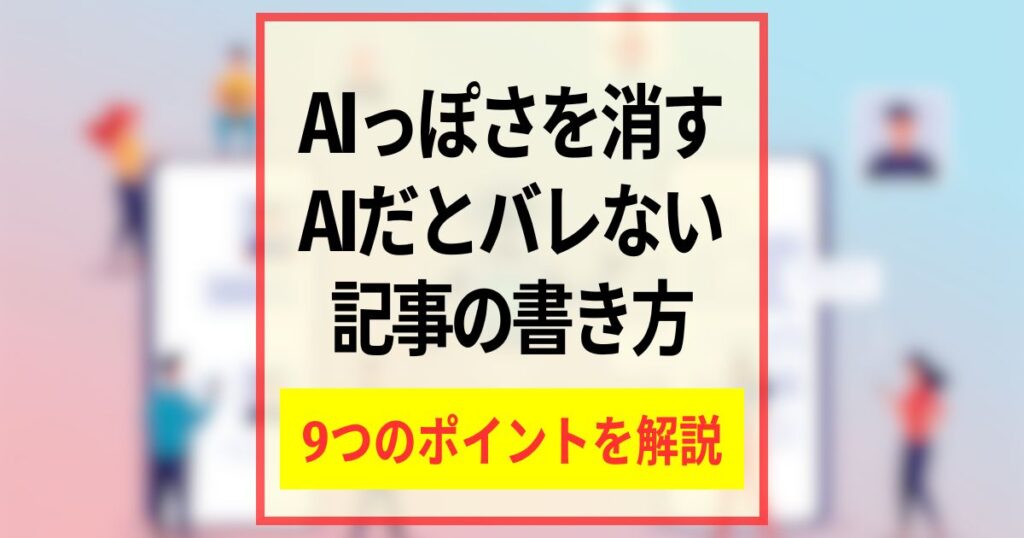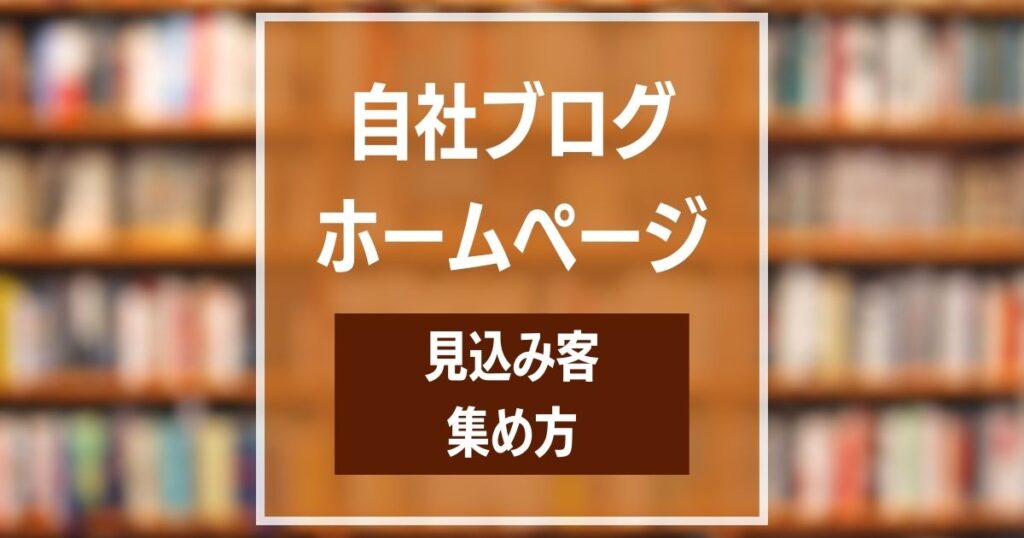- WEB記事の校正・校閲はSEO評価を高めるためにも重要
- 網羅的に校正・校閲することで記事の品質が一気に高まる
- 校正・校閲にもAIを導入し、人間と協業することが大切
[char no=”1″ char=”トール”]今回のテーマは『』について![/char]
どうもー!トールです(@tooru_medemi)
WEB記事の品質を左右する文章校正は、単なる誤字脱字のチェックにとどまらず、SEO評価やブランド価値にも直結する重要な作業です。
しかし、校正・校閲・推敲・編集の違いや、効率的な校正・校閲の手順について、体系的に理解している方は少ないのではないでしょうか。
現在のAI時代において大量生成されるコンテンツの中で「差別化」を図るには、AIと人間の協業による丁寧な校正作業が欠かせません。
そこで本記事では、WEB記事に特化した文章校正のやり方、プロンプトの一例を紹介します。
WEB記事に欠かせない文章校正とは?
誤字脱字や誤情報は、読者の信頼を一瞬で失う致命的なミスです。
文章校正は、これらの表層的なエラーを防ぎながら、検索エンジンが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の評価を底上げする重要なプロセスといえるでしょう。
とはいえ、単なるミス探しにとどまらないのが、WEB記事における校正の奥深さです。
校正・校閲・推敲・編集の違い
文章を整える作業には、校正・校閲・推敲・編集という4つの異なるアプローチがあります。
それぞれの定義と役割を明確に理解することで、効率的な文章改善が可能になるでしょう。
| 作業名 | 対象 | 主な内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 校正 | 文字・表記 | 誤字脱字、送り仮名、句読点の修正 | 編集者・校正者 |
| 校閲 | 内容の正確性 | 事実確認、専門用語の検証、データの照合 | 校閲者・専門家 |
| 推敲 | 文章の質 | 語感・リズムの調整、読みやすさの向上 | 執筆者本人 |
| 編集 | 全体構成 | 構成の組み替え、情報の取捨選択 | 編集者 |
※横スクロールで全部見れます
これらの境界を明確にすることで、AIツールと人間の役割分担を効果的に決められるようになります。
表層的な校正作業はAIに任せ、内容の深い部分は人間が担当するという分業体制が、効率と品質の両立を可能にします。
SEOとブランドに与える影響
誤情報や重複表現は、Googleのコアアップデートで品質評価を下げる要因として認識されています。
検索エンジンは年々、コンテンツの正確性と独自性を重視するようになっており、校正不足の記事は順位下落のリスクを抱えることになるでしょう。
一方、WEB記事を校正することで、以下のような「SEOにプラスの影響」を与えます。
- 文章の一貫性向上による直帰率の低下
- サイト内回遊率の改善
- 検索順位の安定化
- E-E-A-T評価の向上
ブランドトーンを守ることは、指名検索や再訪率の向上に直結します。読者は一貫した文体やトーンマナーに親近感を覚え、そのメディアのファンになっていきます。
それでも、多くの企業が見落としがちなのが、校正・校閲プロセス自体の透明性です。
実は、校正・校閲のプロセスを公開することで「透明性」という新たな価値が生まれます。どのような基準で記事をチェックし、品質管理を行っているかを読者に示すことで、信頼が資産として蓄積されていきます。
編集後記やメイキング記事として校正・校閲の裏側を見せることで、読者との距離が縮まり、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。
▼あわせて読みたい
SEOライティングのやり方を11ステップで解説!検索1位を量産できた書き方のコツ
WEB記事の文章校正・校閲のやり方【7ステップ】
WEB記事の文章校正・校閲は、7つのステップでチェックすることが重要です。
このアプローチにより、見落としがちな箇所も含めて網羅的に品質を担保でき、再修正のループを防げます。
- 内容・構成レベル
- 文体・表現レベル
- 文法・表記レベル
- 体裁・フォーマットレベル
- 一貫性・スタイルガイド遵守
- ファクトチェック・リサーチ
- 納品前の最終確認
これら7つのステップを、ここから詳しく解説します。
内容・構成レベル
論旨の一貫性は、記事全体の説得力を左右する重要な要素です。
主張と各段落の因果関係が論理的につながっているか、矛盾や飛躍がないかを慎重に確認します。
【内容・構成レベルのチェックポイント】
□ 主張と根拠の論理的なつながり
□ 段落間の自然な流れ
□ 1段落1トピックの原則
□ PREP法での論理構成
□ CTAへの導線の一貫性
見落としがちなのが「読後行動(CTA)への導線」です。
記事を読み終えた読者に、次にどのような行動を取ってもらいたいのか、その導線が途中で途切れていないか、最後まで一貫しているかを点検する必要があります。
資料請求、会員登録、関連記事への誘導など、目的に応じたCTAが自然に配置されているか確認しましょう。
文体・表現レベル
語尾の統一は、文章全体の印象を大きく左右します。
敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)の混在を避け、同じ語尾が3回以上連続しないよう注意しましょう。
| 基本形 | バリエーション |
|---|---|
| です | でしょう、といえます、のです |
| ます | ません、ましょう、ました |
| である | だろう、といえる、のだ |
| する | しない、したい、すべき |
※横スクロールで全部見れます
トーン&マナーについては、ブランドガイドラインに従いつつ、読者層に合わせた表現を心がける必要があります。
さらに、文章のリズムも重要な要素です。長文が連続すると読者の集中力が途切れやすくなるため、要所で改行や箇条書きを活用し、視覚的な休憩ポイントを設けましょう。
生成AIにより作成した文章には特有の癖があり、いわゆる「言い換え過多」で本来の意味が薄れてしまうケースが少なくありません。
- 同じ意味の動詞の過度な言い換え(実施する、行う、遂行する)
- 不自然な接続詞の多用
- 冗長で回りくどい表現
- 文脈に合わない難解な語彙
人間の校正者は、このような機械的な言い換えを見つけ出し、より自然で伝わりやすい表現に修正する役割を担います。
文法・表記レベル
助詞・助動詞の誤用や、主語と述語のねじれは、読者の理解を妨げる大きな要因となります。
これらはAIなどのツールである程度発見できますが、文脈を考慮した最終判断は人間が行う必要があるでしょう。
【表記統一のチェックリスト】
□ 数字:半角・全角の統一
□ 単位:%、℃、円などの表記
□ 外来語:カタカナ表記の統一
□ 送り仮名:文化庁の基準に準拠
□ 漢字とひらがなのバランス
また、JTF(日本翻訳者協会)の最新スタイルガイドと、業界独自のルールが異なることがあります。
このような場合は、両者を整理し、自社独自の表記ルールとしてAIに組み込むことで効率化が図れます。
以下の表は、業界別で表記が異なる言葉の一例です。
| 一般向け | IT業界 | 医療業界 |
|---|---|---|
| ウェブ | Web | ウェブ |
| お客様 | ユーザー | 患者様 |
| 作る | 構築する | 調製する |
※横スクロールで全部見れます
体裁・フォーマットレベル
見出し階層の整合性は、記事の構造を明確にする基本要素です。
H2→H3→段落という親子関係が崩れていないか、見出しレベルの飛び越しがないかを確認します。
【適切な見出し構造の例】
H1: 記事タイトル
├─ H2: 大見出し1
│ ├─ H3: 小見出し1-1
│ └─ H3: 小見出し1-2
└─ H2: 大見出し2
├─ H3: 小見出し2-1
└─ H3: 小見出し2-2
箇条書きや表については、記号の統一はもちろん、スマートフォンでの表示を考慮した可読性のチェックも欠かせません。
特に、モバイルファーストインデックスが標準となった現在、スマートフォンでの表示速度と操作性は、記事の成功を左右する重要な要素となっています。
一貫性・スタイルガイド遵守
WEB記事においても「一過性」や「スタイルガイド」を守ることは、ブランドイメージを崩さないためにも重要です。
記事ごとに表記ルールやトーン&マナーがバラバラだと、読者からの信用・信頼性は高まりません。
用字用語集やブランドNGワードなどを、AIツールや自動判定ツールに登録することで、表記の統一性を効率的に保てます。
- 表記ルール(数字、単位、外来語)
- 禁止用語・推奨用語リスト
- トーン&マナーの指針
- 文体の統一基準
- 業界特有の専門用語集
社外ライターとの協業が多い場合は、独自の「校正セルフチェックシート」を配布することで、納品前の品質を向上させられます。
このシートには、よくある間違いのパターンや、自社特有の表記ルールをまとめておくと便利です。
スタイルガイドは一度作って終わりではありません。定期的な見直しと更新により、時代の変化や読者ニーズの変化に対応していく必要があります。
たとえば、ジェンダーに配慮した表現や、多様性を尊重する言葉遣いなど、社会的な価値観の変化を反映させることも重要でしょう。
ファクトチェック・リサーチ
WEB記事制作にも生成AIの活用が広がってきた今、ファクトチェックとリサーチは絶対に欠かしてはいけないポイントです。
一次情報源として、省庁や学会などの公的機関を優先的に参照し、3年以上前のデータには必ず注釈を付けます。
- 政府機関・省庁の公式サイト(go.jp)
- 大学・研究機関の発表(ac.jp)
- 地方自治体の公式情報(lg.jp)
- 業界団体・学会の公式資料
- 大手メディアの報道(複数確認)
ファクトチェックの重要性は年々高まっています。消費者庁は、インターネット上の誤情報や偽サイトなどに対する注意喚起を積極的に行っており、正確な情報提供がブランドの信頼性向上につながることを示しています。
特に注意すべきは、生成AIが提示する情報の検証です。AIは時として正確でない情報を、もっともらしく提示することがあり、これを「ハルシネーション」と呼びます。必ず複数の信頼できるソースでクロスチェックを行い、事実誤認を防ぎましょう。
法規制については、改正景品表示法や個人情報保護法、AI利用ポリシーなど、常に最新の情報にアップデートする必要があります。
納品前の最終確認
ついつい忘れがちですが、多デバイスでのプレビューは必須の作業です(パソコン、タブレット、スマホなど)。
以下のチェックリストを活用して、漏れなく確認を行いましょう。
【最終確認チェックリスト】
□ デスクトップ表示の確認
□ タブレット表示の確認
□ スマートフォン表示の確認
□ 改ページ位置・余白の調整
□ スクリーンリーダーでの読み上げテスト
□ フォーム・外部リンクの動作確認
□ 構造化データの検証
□ 画像の代替テキスト設定
とはいえ、見落としがちなのが構造化データの確認です。
記事URLを公開する前に、Googleの「構造化データテストツール」でリッチリザルトの表示を確認しましょう。
適切に設定されていれば、検索結果での視認性が向上し、クリック率の改善につながります。
AIで文章校正・校閲を効率化
AIツールは、誤字脱字の検出や言い換え候補の提示において、人間を上回る精度とスピードを発揮します。
これらの下流作業をAIに任せることで、作業時間を大幅に短縮できるでしょう。
AIツールと人間の役割分担について、一例を以下に挙げました。
| 作業内容 | AI担当 | 人間担当 |
|---|---|---|
| 誤字脱字チェック | ◎ | △ (最終確認) |
| 表記統一 | ◎ | △ (ルール設定) |
| 文法チェック | ○ | ○ (文脈判断) |
| 事実確認 | △ | ◎ (検証必須) |
| トーン調整 | △ | ◎ (ブランド理解) |
| 構成改善 | × | ◎ (全体最適化) |
※横スクロールで全部見れます
一方で、人間は文脈の理解やトーンの調整、事実確認といった高度な判断が必要な領域に集中することで、記事の品質担保と差別化を図れます。
また、プロンプトの最適化により、AIによる校正・校閲の精度は劇的に向上します。
ただし、AIはあくまでも支援ツールであり、最終的な判断は人間が行う必要があることを忘れてはいけません。
文章校正・校閲のプロンプト例
効果的なプロンプトを活用することで、AIツールの能力を最大限に引き出すことができます。
以下に、プロンプトの一例を紹介します。カスタマイズしてご利用ください。
【基本的な校正プロンプト】
「以下の文章を敬体で統一し、SEOキーワードを残したまま冗長表現を削減してください」
【構造改善プロンプト】
「H2/H3見出し構造を保持したまま、各段落に要約文(50字以内)を追加してください」
【読者層最適化プロンプト】
「ブランドトーンを"専門的だが親しみやすい"に設定し、専門用語には( )内で簡単な説明を加えてください」
最も重要なのは、自社独自のルールをAIに学習させることです。
「自社スタイルガイド遵守:」という前置きを付けて、具体的なルールを明示することで、AIの出力を自社の基準に合わせられます。
また、AIで文章を作成するときに、以下の指示をプロンプトに組み込むと効果的です。
- 数字は3桁ごとにカンマ
- 企業名は正式名称を使用
- 引用は必ず出典を明記
- 見出しは体言止めで統一
- 一文は60字以内を目安
このように、プロンプトをカスタマイズしていくことで、AIツールが自社専用の校正アシスタントとして、より機能するようになるでしょう。
▼あわせて読みたい
AIっぽい文章が「バレる」9つの特徴とバレない書き方