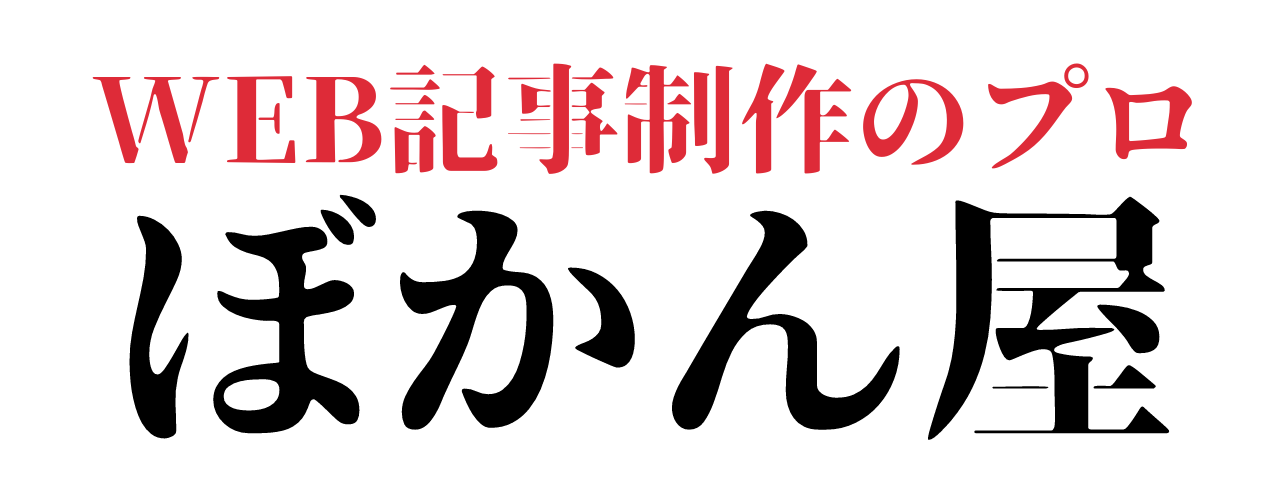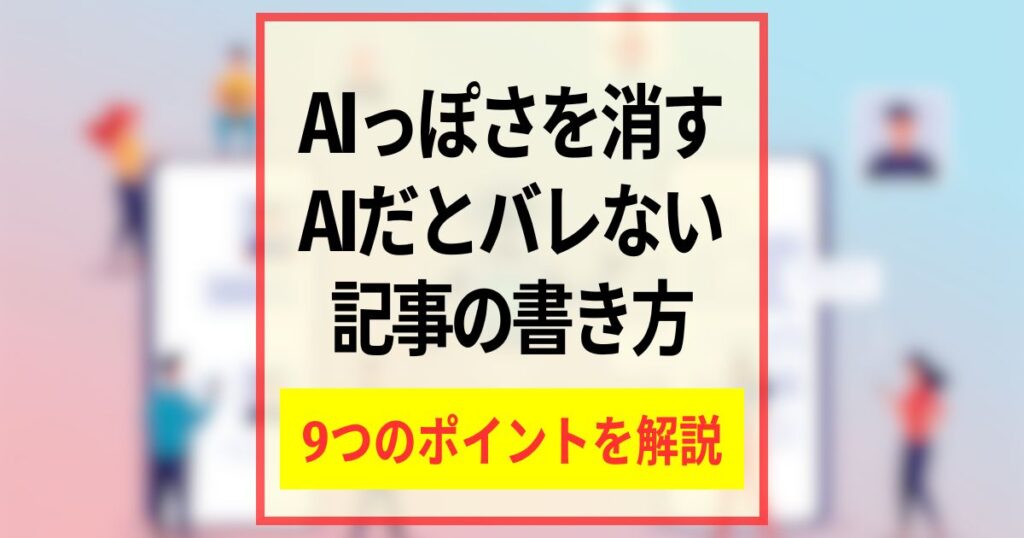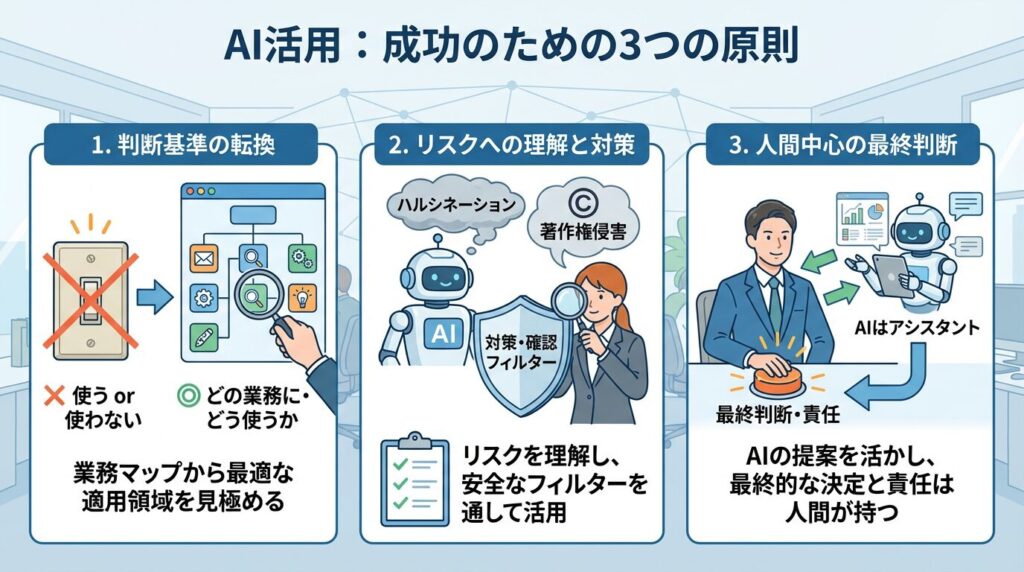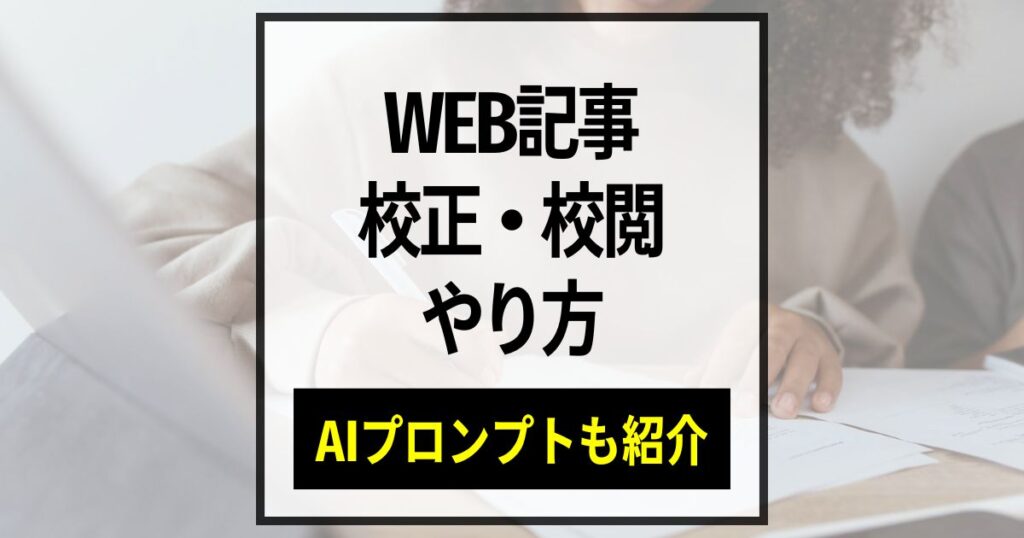- AIっぽさの正体は語尾の単調さと感情の欠如
- 5W1Hで体験談を入れれば信頼性が劇的に向上
- プロンプト調整と人の目チェックで自然な文章に
[char no=”1″ char=”トール”]今回のテーマは『文章からAIっぽさを無くす方法』について![/char]
どうもー!トールです(@tooru_medemi)
「この文章、AIで書いたでしょ?」最近、こんな指摘を受けたことはありませんか。
ChatGPTをはじめとするAIライティングツールの普及により、多くの人がAI生成文章の特徴を見抜けるようになってきました。
- 語尾の単調な繰り返し
- 感情表現の欠如
- 抽象的な例示 など
AIっぽい文章には明確な特徴があり、これらが読者の信頼を損ない、SEOにも悪影響を与える可能性があります。
しかし、AIツールを完全に使わないというのは現実的ではありません。重要なのは、AIの弱点を理解し、適切に対策することです。
そこで本記事では、AIっぽさを感じさせる9つの要素を詳しく解説し、それぞれを改善する具体的な方法を紹介します。
AIっぽさを感じさせる原因
AIが生成した文章には、特有のパターンや癖が存在します。
それは、確率をベースにした出力、安全性を考えた出力など、以下のような「AIの特性上」による部分が多いです。
【AIの特性による影響】
- 最頻語・最頻構造を選ぶ設計ゆえ、文章が“整い過ぎ”て単調
- 誤情報・偏向を避ける安全策が、曖昧表現や中立羅列を増やす
- 本人の感情を伴うエピソードを語れず、リアリティが乏しい
- 尖った語彙を排除し、結果として無味乾燥っぽい文体に
とはいえ、これらの特徴を理解すれば、より自然な文章作成が可能になるでしょう。
以下の表で、AIっぽさを感じさせる主な要因を整理しました。
| 要素 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 語彙・文体の均一性 | 同じような難易度の言葉ばかり使用 | 「効果的です」「重要です」「必要です」の繰り返し |
| 語尾が連続する単調さ | 「です・ます」調の機械的な反復 | 「〜です。〜です。〜です。」が3文以上続く |
| 文章構造が型通り | 序論→本論→結論の教科書的展開 | 「まず」「次に」「最後に」の定型パターン |
| 論理展開に無駄がない | 寄り道や余談が一切ない直線的な構成 | A→B→Cの完璧な論理展開のみ |
| 一次体験の欠如 | 具体的な経験談や現場感がない | 「一般的に〜と言われています」の多用 |
| 感情の欠如 | 喜怒哀楽が感じられない平坦な文体 | 感嘆詞や感情を表す副詞の不在 |
| 引用データの曖昧さ | 出典や時期が不明確な数値の提示 | 「ある調査によると」で済ませる |
| 例示が抽象的 | 固有名詞や具体的な数値が出てこない | 「例えば、ある企業では」という表現 |
| エビデンスが薄い/出典が不明 | 根拠となる資料へのリンクがない | 「多くの専門家が」という漠然とした主語 |
※横スクロールで全部見れます
実のところ、これらの特徴は2024年頃から多くのSEO担当者やライターの間で問題視されるようになっています。
Google検索のアルゴリズムも、こうした機械的な文章を識別する精度が向上しているため、検索で上位表示を狙うなら対策が不可欠でしょう。
AIっぽさを薄める方法
AIが生成した文章の不自然さを改善するには、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。
語彙の多様化から文章構造の工夫、感情表現の追加まで、総合的な対策を講じることで、読者に違和感を与えない自然な文章が作成できるでしょう。
以下は、AIっぽさを薄める主な施策例です。
| 施策 | 主な内容 |
|---|---|
| 語彙・文体のバリエーションを増やす | ・漢語・和語・カタカナ語の比率を段落ごとに揺らし、同義語・擬音語・口語表現を意図的に挿入 ・1文50字超は分割してリズムを可変に |
| 語尾パターンをランダマイズする | ・「です/ます/でした/ですよ」を交互に配置し、同語尾3連続を検知して正規表現で自動置換 ・読了率A/Bテストで最適パターンを検証 |
| 文章構造に”余白”とズレを入れる | ・教科書的3部構成を崩して問い掛け→迂回→回収の流れに ・接続詞の位置をランダム化し、見出し間に1行ブレイクや引用枠を挿入 |
| 意図的な迂回・脱線で論理に起伏を付ける | ・反論→再説明→結論のジグザグ展開を1章1回実施 ・体験エピソードを挟み”間”を作り、読者の思考を促す未完フレーズで締める |
| 一次体験を具体的に差し込む | ・5W1Hテンプレで失敗談・現場描写を抽出し、固有名詞・日時・場所を必ず含める ・体験談を導入200字内に置き共感を獲得 |
| 感情語と感情曲線を織り込む | ・ポジ・ネガ語を交互に配置し感情波形を生成 ・「焦り」「高揚」など感情ラベル語を明示し、読者質問で感情シミュレーションを促す |
| データは必ず日付つき出典を明示する | ・官公庁・業界団体の統計をYYYY/MM/DD付きで引用 ・リンク切れチェックを月次ジョブ化し、古いデータはアラートで即時差し替え |
| 例示を固有名詞・数字で具体化する | ・「たとえば◯◯」→「2025年4月、トヨタは…」へ置換 ・数値は対象・比較軸・単位をセットで提示し、図表・写真を挿入し視覚情報を補完 |
| 公的・一次ソースでエビデンスを補強する | ・学術論文DOI・ホワイトペーパーURLを明記 ・自社ABテスト結果をスクショ+数値で提示し、C2PA署名で改変履歴を保証し信頼度向上 |
※横スクロールで全部見れます
それでは、具体的にどのような方法でAIっぽさを薄めていけばよいのか、9つの実践的なテクニックを詳しく見ていきましょう。
語彙・文体のバリエーションを増やす
文章の単調さを打破するには「語彙の多様性」がポイントになります。
漢語・和語・カタカナ語の比率を段落ごとに変化させることで、いわゆる「読者の飽き」を防げるでしょう。
漢語・和語・カタカナ語の使い分け(例)
- 第1段落:漢語中心(検討する、考察する、分析する)
- 第2段落:和語中心(考える、思いめぐらす、見つめる)
- 第3段落:カタカナ語も混在(ブレインストーミング、アプローチ)
ある段落では「検討する」「考察する」といった漢語を使い、次の段落では「考える」「思いめぐらす」という和語に切り替え、別の段落では「ブレインストーミング」などのカタカナ語も織り交ぜれば、文章にメリハリが生まれます。
また、擬音語・口語表現を意図的に挿入することで、文章は生き生きとしてきます。
擬音語・口語表現の活用例
- 「効果がある」→「ガツンと効く」「じわじわ浸透する」
- 「理解する」→ 「腑に落ちる」「ピンとくる」
このような感覚的な表現は、読者の感情を動かしたり、共感を呼びやすかったりします。
また、絶対ではありませんが「1文が50字を超える」場合は、思い切って分割しましょう。
短文と長文を交互に配置すれば、読むリズムに変化が生まれ、最後まで読み進めてもらいやすくなります。
語尾パターンをランダマイズする
同じ語尾の連続は、AIっぽさの最たる特徴といえるでしょう。
「です/ます/でした/ですよ」などを交互に配置し、同語尾が3回以上続かないよう注意が必要です。
| パターン | 使用例 | 効果 |
|---|---|---|
| 断定形 | 〜です、〜ます | 基本の丁寧語、安定感 |
| 過去形 | 〜でした、〜ました | 体験談や事例紹介に |
| 推量形 | 〜でしょう、〜かもしれません | 読者との対話感 |
| 体言止め | 〜が重要、〜という結果 | リズムの変化 |
| 疑問形 | 〜でしょうか? | 読者への問いかけ |
※横スクロールで全部見れます
語尾の工夫として「体言止め」や「疑問形」の使用も効果的です。
また「〜だろうか」「〜かもしれない」といった推量表現を混ぜることで、読者との対話感も演出できるでしょう。
文章構造に”余白”とズレを入れる
教科書的な「3部構成」や「RPEP法」は、論理的である反面、予定調和的で退屈になりがちです。
これらの構成を利用すると、以下の流れで文章を論理的に展開できます。
【3部構成】
- 序論(問題提起)
- 本論(解決策)
- 結論(まとめ)
【PREP法】
- P(結論)主張を端的に述べる
- R(理由)なぜそう言えるのか説明
- E(具体例)実例や数値で裏付け
- P(結論)改めて主張を強調
ただし、こういった構文ばかりを使っていると、やはりAIっぽさを醸し出してしまいます。
あえて問いかけから始め、一度話を逸らしてから本題に戻るような構成にすると、読者の興味を引き続けられるでしょう。
- 問いかけ(読者の共感)
- 一度話を逸らす(関連エピソード)
- 本題に戻る(核心的な解決策)
- 新たな問いで締める
また、接続詞の位置も工夫次第で印象が変わります。
「しかし」を文頭に置くのが定石ですが、「世間では〜と言われている。しかし、実際のところは」のように文中に配置すれば、リズムに変化が生まれます。
見出し間に1行の空白や引用枠を挿入するのも効果的です。視覚的な休憩ポイントを設けることで、長文でも圧迫感を与えずに済むでしょう。
▼あわせて読みたい
わかりやすい文章の書き方!
意図的な迂回・脱線で論理に起伏を付ける
AIによる完璧すぎる論理展開は、かえって不自然さを生みます。
反論を提示してから再説明し、最終的に結論に至るようなジグザグ展開を、1回は入れてみましょう。
「確かに〜という意見もある。だが、よく考えてみると」といった展開は、読者の思考を活性化させます。
【ジグザグ展開の基本構造】
- 主張の提示:「〜が効果的だ」
- 反論の紹介:「確かに〜という意見もある」
- 反論への回答:「だが、よく考えてみると」
- 深掘り:「実際のデータを見ると」
- 結論:「やはり〜が重要だ」
また、体験エピソードを挟むことで、論理の合間に「間」を作ることも大切です。
読者の思考を促す「未完フレーズ」で締めるのも一つの技法でしょう。
すべてを説明し尽くすのではなく、「では、あなたの文章はどうだろうか…」のように、余韻を残すことで記憶に残りやすくなります。
一次体験を具体的に差し込む
AIが苦手としている文章作成の1つが、具体的な体験談を書くことです。
AIっぽさを薄めるために「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」を意識して、自分が経験したことなど「現場のリアルな様子」を描写しましょう。
たとえば、以下の文章からは「AIっぽさ」が感じられませんか?
【AIっぽさがある文章の例】
AI記事の見分け方について、ある専門家が重要な指摘をしていました。
その内容によると、具体的な失敗談がない記事は疑うべきだということです。
確かに、AIは成功事例ばかりを提示する傾向があり、人間らしい失敗経験が含まれていないことが多いようです。
これを、5W1Hを意識してテコ入れしてみたところ、以下のように仕上がりました。
【5W1Hを使った場合】
2024年11月15日、東京ビッグサイトで開催されたコンテンツマーケティングEXPOで、株式会社デジタルマーケティング研究所の山田太郎氏が登壇しました。
『なぜあなたの記事は読まれないのか?AI時代のコンテンツ戦略』と題された講演の中で、山田氏は実際のクライアント事例を示しながら、『具体的な失敗談がない記事は疑え』と力説していました。
会場には約300名のマーケターが集まり、熱心にメモを取る姿がとても印象に残っています。
このように、固有名詞、日時、場所を含めることで、文章の信憑性が格段に上がります。
さらに「約300名のマーケターが集まり」「熱心にメモを取る姿」といった現場の様子を加えるだけで、読者はその場にいるかのような臨場感に感じられるでしょう。
また、こういった体験談は「導入部分(リード)」に配置すると、読者の共感を得やすくなります。
たとえば、冒頭で「私も以前は〜で悩んでいました」と切り出せば、同じ悩みを持つ読者はきっと最後まで読んでくれるでしょう。
感情語と感情曲線を織り込む
AIが生成する文章の最大の弱点は「感情表現の欠如」にあります。
人間が書く文章には、喜び、不安、驚き、落胆といった感情の起伏が自然に織り込まれていますが、AIは論理的に正しい情報を淡々と並べるだけになりがちです。
単なる情報の羅列では、読者の心を動かすことはできません。平坦な文章に感情の起伏を加えるために、ポジティブ・ネガティブな感情語を交互に配置することが効果的です。
| 段階 | 感情状態 | 使用する感情語(例) |
|---|---|---|
| 導入 | 不安・疑問 | 「戸惑った」「途方に暮れた」 |
| 展開① | 期待・希望 | 「ワクワクした」「光が見えた」 |
| 展開② | 挫折・焦り | 「がっかりした」「焦りを感じた」 |
| 解決 | 発見・高揚 | 「ひらめいた」「興奮を抑えきれなかった」 |
| 結論 | 安堵・確信 | 「ホッとした」「確信に変わった」 |
※横スクロールで全部見れます
「ワクワクした」「不安になった」「ホッとした」といった感情表現を使うことで、読者も追体験しやすくなるでしょう。
また、読者に「もしあなたがこの状況だったら、どう感じるでしょうか」と質問を投げかけるのも有効です。
文章や記事を読んでいる人たちは「受動的」になりがちですが、感情に訴えかけることで能動的な体験にも変えられます。
データは必ず日付つき出典を明示する
曖昧なデータ引用は、AIっぽさの典型例です。
官公庁や業界団体の統計を引用する際は、できる限り「YYYY年MM月DD日」の形式で日付を明記しましょう。
この他にも、データを引用する場合は、以下のことに注意します。
- 出典元の正式名称を記載
- 公開日をYYYY年MM月DD日形式で明記
- URLは公的機関(.go.jp/.ac.jp/.lg.jp)を優先
- データの対象期間を明確化
- 比較対象がある場合は条件を統一
また、リンク切れは信頼性を大きく損なうため、月次でのチェックをルーティン化することが重要です。古いデータを引用し続けていると、記事全体の信頼性が疑われてしまいます。
データの更新頻度が高い分野では、自動アラートシステムの導入も検討すべきでしょう。新しい統計が発表されたら即座に差し替えることで、常に最新の情報を提供できます。
例示を固有名詞・数字で具体化する
AIが生成する文章でよく見られる特徴の一つが、「ある企業では」「多くの人が」といった曖昧な表現の多用です。
これは、AIが学習データから一般化した知識を基に文章を生成するため、具体的な固有名詞や正確な数値を避ける傾向があるからです。
以下のように、抽象的な表現があれば「具体的な表現」へ修正すると良いでしょう。
| 抽象的な表現 | 具体的な表現 |
|---|---|
| ある企業では | 2025年4月、〇〇株式会社では |
| 売上が増加した | 売上が前年同期比23.5%増の1,250億円に増加した |
| 多くのユーザーが | 調査対象1,500名のうち73.2%が |
| 最近の傾向として | 2024年第3四半期以降の動向として |
| 大幅に改善された | 処理速度が従来比4.7倍に向上した |
※横スクロールで全部見れます
数値を提示する際は、対象・比較軸・単位をセットで示すことが大切です。
「売上が増加した」ではなく、「前年同期比で売上高が23.5%増の1,250億円に達した」と書けば、読者は状況を正確に把握できます。
図表や写真を挿入して視覚情報を補完することも忘れてはいけません。複雑なデータは、グラフ化することで理解しやすくなるでしょう。
公的・一次ソースでエビデンスを補強する
AIが生成する文章の特徴的な問題点として「情報源の曖昧さ」があります。
「研究によると」「専門家の意見では」といった漠然とした引用が多く、具体的にどの研究機関の、いつの調査なのかが明示されないケースが目立ちます。
これは、AIが膨大な学習データから情報を統合して生成するため、個別の出典を特定できないことが原因です。
- AIが時として存在しない研究や架空の統計データを「創作」してしまう
- これは「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、もっともらしい嘘を生成してしまうAIの致命的な欠点
- 読者も最近はこうしたAIの特性を理解しているため、出典が曖昧な記事を見ると「AIで書いたのでは?」と疑う
AIっぽさを無くすために「公的ソース」や「一次ソース」を活用すれば、より信頼性を高めることができます。
エビデンスソースは、おおよそ以下の順で信頼度が高いです(あくまでも目安)。
- 学術論文(DOI付き):最も信頼性が高い
- 官公庁統計(.go.jp):公的データとして信頼できる
- 大学研究機関(.ac.jp):学術的裏付けあり
- 業界団体レポート:専門性は高いが中立性に注意
- 企業ホワイトペーパー:有用だが営利目的の可能性
学術論文のDOI、官公庁統計、ホワイトペーパーなどは、あわせて「リンクテキスト」も設置します。
リンクテキストは通常、色や下線などの視覚的な表現で通常のテキストと区別され、URLと関連づけられたテキスト文字列です。この関連付けをハイパーリンクと呼び、これはウェブをウェブたらしめている基本的な概念のひとつです。
自社でA/Bテストを実施した場合は、その結果をスクリーンショットと数値で提示しましょう。実際のデータに基づいた改善提案は、机上の空論よりもはるかに説得力があります。
最近注目されている「C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity)署名」を活用すれば、コンテンツの改変履歴を保証でき、信頼度がさらに向上します。
さらにAIっぽさを無くすには
ここまで紹介した9つの方法を実践すれば、AIっぽさはかなり軽減されるはずです。しかし、それでもまだ不自然さを感じる場合は、より根本的なアプローチが必要になるでしょう。
- AIツールの使い方そのものを見直す
- 人間による最終調整を徹底する
以下では、プロンプトエンジニアリングの観点と、人的リソースを活用した品質管理の2つのアプローチから、さらなる改善方法を解説します。
プロンプトを調整
AIツールを使用する際の「プロンプト(指示文)」の工夫次第で、生成される文章の質は大きく変わります。
単に「〜について書いて」と指示するのではなく、「個人的な体験を交えながら」「読者への問いかけを含めて」といった具体的な条件を加えましょう。
| 要素 | 具体例 | 効果 |
|---|---|---|
| 体験指示 | 「個人的な体験を交えながら」 | 一次情報の追加 |
| 対話指示 | 「読者への問いかけを3回以上含めて」 | 双方向性の演出 |
| 禁止事項 | 「同じ語尾を3回以上使わない」 | AIっぽさの排除 |
| 感情指示 | 「喜怒哀楽を織り交ぜて」 | 感情曲線の生成 |
| 文体指定 | 「時にユーモアを交えて」 | 硬さの緩和 |
※横スクロールで全部見れます
プロンプトには、望ましくない要素を明示的に禁止する指示も効果的です。
「同じ語尾を3回以上使わない」「抽象的な例示を避ける」といったネガティブプロンプトを追加することで、AIっぽさを軽減できます。
文体についても「親しみやすく、時にユーモアを交えて」のような指示を加えれば、機械的な印象を和らげられるでしょう。
【プロンプト(例)】
あなたは5年間SEOライティングに携わってきた30代のWebマーケターです。
以下の条件で「AIライティングツールの活用法」について800字程度で執筆してください。
【必須条件】
1. 冒頭200字以内に、あなたが実際に体験した失敗談を含める
2. 具体的な企業名、日付、数値を3つ以上含める(例:2024年9月15日、株式会社〇〇、売上23.5%増)
3. 感情の変化を表現する(最初は不安→試行錯誤で焦り→成功して喜び)
4. 読者への問いかけを2回以上入れる
5. 語尾は「です/ます/でしょう/かもしれません/〜という結果に」など5種類以上使い分ける
【禁止事項】
– 「一般的に」「多くの場合」などの曖昧な表現は使わない
– 同じ語尾を3回連続で使わない
– 「効果的です」「重要です」「必要です」の安易な繰り返しを避ける
– 教科書的な「まず」「次に」「最後に」の構成にしない
【文体】
– 時々「正直なところ」「実は」などの本音を挟む
– 1文は50字以内を基本とし、リズムを変える
– 専門用語を使ったら、すぐに分かりやすい言葉で言い換える
最終的に人の目でチェック
どれだけ優れたAIツールを使っても、最終的な品質保証は「人間の目」に委ねられます。
特に注目すべきチェックポイントは、文章の流れの自然さ、感情表現の適切さ、そして読者視点での違和感の有無です。
| チェック項目 | 確認ポイント | 修正例 |
|---|---|---|
| 文章の流れ | 論理の飛躍はないか | 接続詞や補足説明を追加 |
| 感情表現 | 不自然な感情語はないか | 文脈に合った表現に変更 |
| 語尾の連続 | 3回以上同じ語尾か | バリエーションを追加 |
| 具体性 | 抽象的な表現が多いか | 数字や固有名詞を追加 |
| 読者視点 | 専門用語が多すぎないか | 平易な言葉に置き換え |
※横スクロールで全部見れます
音読してみると、不自然な箇所が見つかりやすくなります。
校正の際は、複数人でのクロスチェックが理想的でしょう。書いた本人では気づきにくい違和感も、第三者の目なら発見できることが多いからです。
最後に、読者からのフィードバックも貴重な改善材料となります。コメント欄やアンケートで得られた意見を真摯に受け止め、次回の執筆に活かすことで、より人間味のある、読者に寄り添った文章が書けるようになるでしょう。
▼あわせて読みたい
文章力をアップする方法!