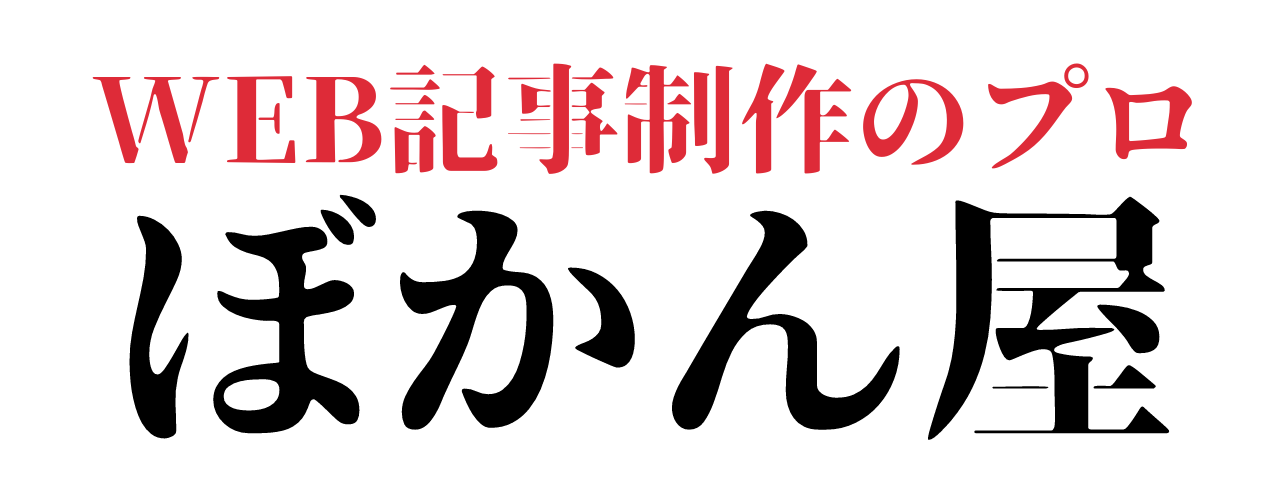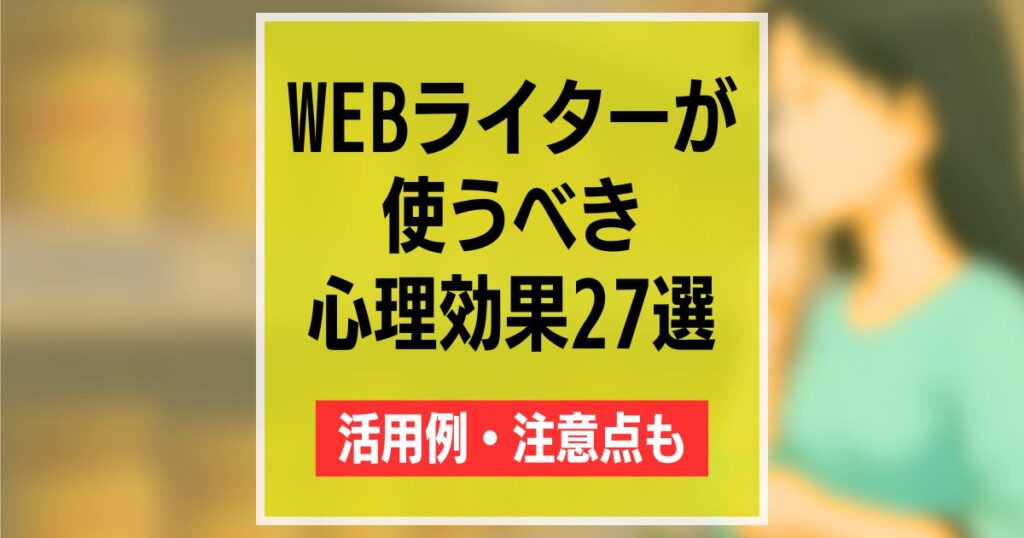ずっと仕事が絶えないコピーライターやセールスライターは、まず「人の心を動かす」ことに最大限注力して文章を書いています。
いくらキレイで読みやすい文章を書いたとしても、読者の心が動かなければ商品やサービスはまったく売れないことを知っているからです。
一流のライターは、心理効果を狙って文章や記事を書いている人たちばかりです。
しかし、ライティング初心者でも本記事で紹介する「心理学的アプローチ」を取り入れるだけで、
- ついつい買ってしまう
- 喜んで自分から買う
- ファンになる
- リピーターになる
- 周りに紹介してくれる
といったことが、実際に起こりはじめます。
読者心理を意識してライティングをするだけで「書くほど売り上げが伸びる」「絶え間なく仕事の依頼が舞い込む」といった、売れっ子ライターに成長できます。
この記事で紹介している「ライティングに活用できる心理効果」をぜひ参考にしてください。
ライティングに使える心理効果【一覧】
ライティングに活用できる心理効果27選を、一覧にしました。
それぞれの詳細については、この記事で解説しています。
| 心理効果 | 概要 | 簡単な例 |
| 返報性の原理 | 先に好意や利益を受けると「お返ししなくては」と感じる心理 | メルマガ登録時に無料特典を渡し、「もらったから登録しよう」と思わせる |
| 社会的証明 | 多くの人が利用している事例を示すと安心感を持ちやすい心理 | 「○万人が選んだ人気商品」「レビュー件数が圧倒的」などの実績データを提示 |
| 希少性の原則 | 数量限定・期間限定のものを「今手に入れないと損」と感じやすい心理 | 「残り〇個」「本日限り」などを強調し、購買意欲を高める |
| 権威の原理 | 専門家や有名人が推奨すると信頼しやすくなる心理 | 「博士号取得者のコメント」や「業界受賞歴の明示」で説得力を高める |
| 一貫性の原理 | 一度表明した意見や態度に沿って行動を続けたくなる心理 | 記事冒頭で「賛成ですよね?」と質問し、小さな“Yes”を積み重ねて最終的な決断へつなぐ |
| 好意の原理 | 好ましい・共感できる相手の提案を受け入れやすい心理 | 読者の悩みに寄り添う文章で親しみを育み、商品提案への抵抗を下げる |
| 一体感(ユニティ)の原則 | 「同じグループだ」と感じる相手には協力しやすい心理 | 「○○仲間の皆さんへ」と呼びかけ、読者に所属意識を持ってもらう |
| 恐怖訴求 | リスクや不安を提示して「放置すると大変」と警鐘を鳴らし、行動を促す | 「このままだと将来的に××の危険があります」と伝え、商品を解決策として提示 |
| ポジティブ訴求 | 明るい未来像や成功イメージを示し、期待感から行動を誘発する | 「受講後は未経験から高収入エンジニアになれる可能性が広がる」と伝える |
| 怒り・ネガティブ感情の訴求 | 不満や憤りを共有し、「何とかしなくては」と解決意欲を高める手法 | 「環境破壊の理不尽を許さない!」と訴え、寄付やアクションを促す |
| 驚き・意外性の活用 | 常識を覆す事実で「え、そうなの?」と興味を引き、読者を引き込む | 「実は運動より○○がダイエットに効果的!」と伝え、続きを読ませる |
| アンカリング効果 | 最初に提示された情報が基準となり、その後の判断が変わる心理 | 「定価1万円→特別価格7000円」と先に高額を示し、お得感を強調する |
| 損失回避の心理 | 「得をする喜び」より「損を避けたい」感情に強く影響されやすい心理 | 「今買わないと割引が終了し、定価で購入することになる」と損失を意識させる |
| 初頭効果 | 最初に得た情報が、その後の印象や判断を大きく左右する心理 | 冒頭で読者の悩みに直結する問いかけを行い、関心を引き続ける |
| 確証バイアス | 自分の信念を裏付ける情報ばかり選び、反対の証拠を無視しがちな心理 | 環境意識の高い読者に「この製品はあなたのエコ志向に合致します」と寄り添う |
| ツァイガルニク効果 | 未完了のまま中断された事柄のほうが、記憶に残りやすい心理 | 「詳しい手順は後述します」とすぐに答えを出さず、最後まで読ませる |
| 単純接触効果 | 何度も目にする対象に親近感を持ちやすい心理 | 本文中で商品名やブランド名を繰り返し自然に登場させ、馴染みをつくる |
| ピーク・エンドの法則 | 体験の評価は「最も印象的な場面」と「終わり際」で大きく決まる | 中盤で感動的エピソードを挟み、最後に前向きなメッセージで締める |
| カクテルパーティー効果 | 周囲が雑音でも、自分に関係する言葉には自然と意識が向く心理 | 「忙しいワーキングマザーのあなたへ」と呼びかけ、ターゲット層を惹きつける |
| 突出効果 | 多くの情報がある中で、ひとつだけ違う要素が強く記憶に残る心理 | 「唯一の○○対応!」といった表現を強調し、商品やブランドを際立たせる |
| ストーリーテリング | 物語形式で感情移入を深め、論理以上の共感を生む手法 | 利用者のビフォーアフターを物語風に紹介し、読者が自分事としてイメージしやすくする |
| 共感(感情移入) | 読者の悩みを代弁し、「わかってくれている」と安心感を与える心理 | 「朝の満員電車で疲れ切っていませんか?」のように具体的なシーンを描く |
| ミラーリング | 相手の言葉遣いや価値観を映し、心理的距離を縮めるテクニック | SNSのハッシュタグやターゲットの流行語を適度に用い、「同じ世界を共有している」印象を与える |
| フレーミング効果 | 同じ事実でも伝え方次第で受け手の印象が変わる心理 | 「失敗率10%」より「成功率90%」と表現し、ポジティブな印象を与える |
| デフォルト効果 | 初期設定をそのまま受け入れる傾向が強い心理 | メルマガ登録フォームでチェックボックスを既にONにし、外さない限り登録完了になる仕様にする |
| ナッジ(柔らかい誘導) | 押し付けでなく、軽い後押しで自発的な行動を促す行動経済学の概念 | 「もし今すぐ始めたら半年後どう変わるか想像してください」と問いかける |
| デコイ効果 | 比較対象(デコイ)を用いて、狙った選択肢を相対的に魅力的に見せる心理 | ライト・スタンダード・プレミアムの3プランを提示し、あえて不自然に割高なプランを置いて中間プランが選びやすくなる構成にする |
※横スクロールで全部見れます
説得と影響力の心理原則(7つ)
人間は論理的に物事を判断するだけでなく、感情や無意識のバイアスにも左右されやすい生き物です。
そのため、文章で読者を説得するうえでは、ロバート・チャルディーニが提唱した
- 返報性
- 好意
- 社会的証明
- 権威
- 希少性
- 一貫性
- 一体感(ユニティ)
といった、7つの原則を押さえることがポイントになります。
これらの原則を的確に使うことで、購買や登録といったユーザー行動を飛躍的に高められるでしょう。
返報性の原理
返報性の原理とは、誰かから好意や利益を受け取った場合に「お返しをしなければ」と感じる心理傾向を指します。
これは日常の些細な場面でも見られ、サンプル商品や無料キャンペーンで「もらったから返そう」という思いが働くことが典型例です。
ライティングでは、この心理を活かして先に「有用な情報」や「限定特典」を読者へ提示し、読後に行動を促します。
たとえば、
・メルマガ登録フォームで「先着で無料レポートを進呈」と書く
・寄付やクラウドファンディングで「活動報告」を丁寧に記載する
など。
さらに、返報性を活用する際には「過度な期待」を前面に出さないことが大切です。
読者にあからさまに恩返しを求めるような文面は、かえって不信感を招く原因になります。
自然な形で「与える→返してもらいやすい雰囲気をつくる」流れをつくることで、心理的なハードルを下げることに役立つでしょう。
好意の原理
好意の原理は、人が「好き」「共感できる」と思う相手や事柄に心を開き、提案や要望を受け入れやすくなる心理を指します。
文章でも「共感を呼ぶ言葉遣い」や「親しみやすい口調」で書くことで、読者は筆者に対して「自分と同じ感覚を持っている」と感じやすくなります。
さらに、相手の良い点を素直にほめたり、温かみを感じさせるエピソードを紹介することで、読者の警戒心を解きやすくなります。
- 「読者の悩みを理解している」というスタンスを示したうえで「一緒に乗り越えましょう」と寄り添う手法が多用される
このような手法を使うことで、単なる売り込みではなく、助け合いのようなポジティブな印象を与えるわけです。
ただし、お世辞や媚びた表現を乱用すると逆効果にもなりかねません。大切なのは、読者に寄り添いつつも誠実さを伝えることで、自然な好意を生み出すことです。
「好意」と「信頼」はセットで育まれるため、その点を意識したライティングが重要になります。
社会的証明
社会的証明とは、多くの人が利用したり高く評価している事柄を「自分も選んでよい」と感じる心理現象です。
人は他者の判断を参考にすることで安心感を得るため、
- 「○万人が体験」
- 「口コミ評価で平均4.5以上」
などの実績を文章に示すだけで「信用度」が増す傾向があります。
セールスライティングでは、商品ページで「レビュー数が豊富」「ユーザー満足度が高い」と強調するアプローチが一般的です。
また、数字や具体的なデータを出す際には、出典をしっかり示すとさらに説得力が増します。
- 公的機関(政府、官公庁、自治体など)
- 業界団体
- 大企業
- 著名な論文/データ etc
社会的証明を用いる際は「本当に多くの人が支持しているのか」「口コミは信用できるものか」といった、読者の懸念を払拭する配慮が必要です。
誇張や捏造が発覚すると逆効果に陥るため、実態を正しく伝えることで初めて強い説得力が得られます。
権威の原理
権威の原理とは、人が「専門家」や「実績者と認める人物」の意見を、つい信じたくなる心理です。
医師や博士、著名人などから推薦コメントを得ると、その情報の「正確さ」や「信ぴょう性」は大幅に高まるという傾向があります。
ライティングにおいては、
・記事内で「〇〇大学教授の研究結果によれば」といった形で専門家を引用
・商品サイトで「専門資格を持つスタッフがサポートする」と強調
などの手法が該当します。
権威を示す際は、あくまで「読者の求める分野」に精通した人物の見解を引用する点が重要です。
たとえば、ITサービスの信用を高める場合は、セキュリティ分野の専門家や実際に業界で受賞歴のある団体のコメントが効果的でしょう。
ただし、権威を振りかざすような上から目線の言い回しは、逆に反感を買うかもしれません。
さりげなく信頼を裏付けする形で提示することで、読者が「この情報は正しいかも」と納得しやすくなります。
希少性の原則
希少性の原則とは、人は「限られたもの」に対して高い価値を感じやすい心理です。
「在庫僅少」「期間限定」といった表現を加えると、読者は「今手に入れないと後悔するかも」という心理を抱きやすくなります。
- ECサイトでカート付近に「残り2点のみ」という表示を行うと購入率が上がる
- セール終了間際になると急激に売り上げが伸びる
これらは「今逃すと損」という気持ちが、ユーザーの購買行動を後押ししているからです。
ただし、希少性を強調しすぎると「本当は余裕があるのに煽られているだけでは」と警戒されるリスクもあります。
そのため、実在庫や時間制限が事実としてある場合に限り、具体的な数字や日時を提示して「本当の希少さ」を伝えるのが理想的です。
希少性を適度に訴求することで、読者の「早く決断したい」という意識を高め、購入や申し込みへスムーズに誘導する狙いがあります。
一貫性の原理
一貫性の原理は、人が一度取り入れた態度や方針に対して、その後も矛盾なく行動しようとする心理です。
たとえば、一度「応援したい」と表明したプロジェクトなら、最後まで資金協力を続けるという現象が見られます。
また、ライティングでも小さな「Yes」を重ねる手法が効果的です(以下参照)。
- 冒頭で読者に「こう思いませんか?」と問いかける
- 「そうかもしれない」と読者をうなずかせる
- 本文で複数回「頷きポイント」を仕込む
- 最後のCTA(行動喚起)で「あなたなら理解してくれるはず」と後押し
こういう流れにすると、読者は自分がすでに肯定的姿勢を示してきた経緯から「反対しにくい」という心理に至りやすくなります。
一貫性の原理を活用する際に大切なのは、読者を無理やり同意させず、自然に小さなステップを踏ませることです。
押し付けられた一貫性ではなく「読者自身の意志」でステップを踏んでいけると、より信頼感が増していきます。
一体感(ユニティ)の原則
一体感(ユニティ)の原則とは「私たちは同じグループだ」という帰属意識を感じる相手に対して、協力や賛同をしやすくなる心理を指します。
読者が「自分もこのコミュニティの一員だ」と思った瞬間、提案への抵抗感が一気に下がる現象がよく見られます。
たとえば、文章の中で、
- 「○○で頑張る皆さんへ」と呼びかけたり
- 共通の課題や目標を設定して「仲間」と位置づけたり
することで、一体感は高まりやすいです。
【ファンコミュニティやサークルなどの募集ページ】
「あなたも私たちの活動に参加しませんか?」と強調すると「同じ想いを持つ人たちが集まっている場所だ」という認識を読者に持たせられる
この一体感の原則は「希少性」とも相性が良く、たとえば「限定コミュニティ」や「会員限定の〇〇特典」を組み合わせると、さらに強い結束を生む仕組みに発展するでしょう。
一体感を育むうえで大切なのは、具体的な「共通点」の提示です。出身地、趣味、仕事、あるいは悩みなど、読者が自分を重ねられるフックが豊富であるほど、自然に心理的な距離が縮まります。
感情を揺さぶる心理トリガー(4つ)
人間の意思決定においては、理屈だけでなく感情面の影響が大きいとされます。
論理的な説明を聞いて納得したつもりでも、実際の行動を左右するのは「どれだけ心が動かされたか」という部分かもしれません。
そこで、ライティングでは読者の感情を揺さぶる「心理トリガー」を積極的に取り入れることが重要です。
恐怖訴求
恐怖訴求は、読者に「このままだと大きな損失や危険がある」と意識させ、問題に真剣に向き合わせるテクニックです。
たとえば、健康食品の広告で「放置すると将来重篤な症状になる可能性が高まる」と警鐘を鳴らすと、読者は不安になり対策を探し始めます。
ただし、恐怖を煽るだけでは、読者が「怖いから離れよう」と思う可能性もあるため、その先には具体的な解決策や安心材料を提示することが大切です。
「放置すると命の危険があるかもしれないが、この商品ならリスクを軽減できる」
このような流れをスムーズに示すことは、適度な危機感から行動意欲へとつなぐ狙いがあります。
恐怖訴求は強力な一方、誇張や嘘を混ぜると一気に信頼を失う恐れがあります。言い換えれば「正確な情報」と「誠実なトーン」が伴わないと逆効果になりやすいです。
そのため、根拠が示せる範囲で緊迫感を伝えつつ「恐怖に直面しても解決策がある」という形で読者を導くことが望ましいと言えます。
ポジティブ訴求
ポジティブ訴求は、読者に「理想的な未来」や「成功イメージ」を描かせ、前向きな気持ちにさせる手法です。
たとえば「このプログラムを使うと、初心者でも高収入エンジニアになれる可能性が広がる」などのフレーズが典型例として挙げられます。
希望やワクワクをかき立てると、人は「それなら挑戦してみたい」という行動意欲が高まりやすいです。
以下のような場面では、このポジティブ訴求がよく使われます。
- 教育コンテンツ
- 資格講座のLP
一方で、あまりに夢物語に走ると読者が「本当なのか?」と疑問を持つため、以下のように具体的な「成功事例」や「現実的な数字」を補強材料として提示すると説得力がアップします。
・年収が1.5倍になった
・スキルを習得して転職に成功した
・大変な部分もあるが、それを超えるメリットがある
ポジティブ訴求は「読後感」を良くし「商品やサービスへの印象を明るくする」作用があるのもメリットです。
怒り・ネガティブ感情の訴求
怒りや不満などの「ネガティブ感情」に訴えかける手法も、行動を引き出すうえで有効な場合があります。
たとえば、環境問題や社会的な理不尽に対して「このままでいいはずがない」という共感の怒りを読者と共有し、その解決策としてアクションを促す流れです。
「海洋プラスチックが大量に生態系を破壊し続けている。私たちは声を上げなければならない」
こういったトーンで語れば、読者は問題を放置できなくなるかもしれません。
ただし、怒りや不満を煽るだけではストレスを大きくするため「これなら状況を改善できる」という解決策の提示が必要です。
読者の感情をマイナス方向へ動かすときは、逆にプラス方向への転換点をしっかり書くことで「行動しよう」というモチベーションに結びつけられます。
怒りを訴求に利用するのはリスキーでもあるため、事実関係に誤りがないかを慎重に確認し、公正な視点を保つことが肝要でしょう。
[char no=”2″ char=”トール”]あくまでも現状の「不条理」を指摘しつつ「理想のゴールや対策」を示すのがコツです![/char]
驚き・意外性の活用
驚きや意外性は、読者の注意を一気に引き込み、その先を読み進めさせる強力なフックになります。
冒頭や見出しで「運動より○○がダイエット成功の鍵だった!」のように常識を覆す情報を提示すれば、読者は「え、本当なの?」と興味をかき立てられるわけです。
コピーライティングの世界でも、意外な数字や事例を取り上げることで、マンネリ化しがちな文章に新鮮味を持たせる手法は定番です。
- 記驚きを狙いすぎると誇大広告と思われかねない
- これは「論文で裏付けがある」というように根拠を示す
- 「衝撃的な情報」に続く本文が平凡だと、肩透かしを感じさせて逆効果に
読者を引き付けるだけでなく、最後まで興味を持ってもらうために、驚きのネタと本題を無理なくつなぐ流れを設計することがポイントです。
適度な意外性は文章の印象を強くし、SNSなどで拡散されやすい要因にもなるでしょう。
読者の認知バイアス(4つ)
人の判断や思考には、多種多様な認知バイアスが存在します。ライティングでこれらを理解し活用すると、読者の意思決定に影響を与えやすくなります。
一方で、バイアスを利用するだけでなく、読者が本当にメリットを得られるかを吟味しないと信用を失う恐れも否めません。
悪用ではなく、あくまで「読者が合理的な選択をしやすくなるように手助けする」というスタンスが望ましいでしょう。
アンカリング効果
アンカリング効果は、最初に見た数字や情報が心の中で「基準(アンカー)」になり、その後の判断や評価を大きく左右する現象です。
セールスライティングでは、高い定価を先に見せてから実際の販売価格を提示すると、お得感を抱きやすいという手法がよく使われます。
たとえば、以下の方法が挙げれます。
「定価1万円→特別価格7000円」と書くだけで、読者は「3000円も安い」と感じ、購入に踏み切りやすくなる
サービスプランを複数用意し、一番高額なプランをアンカーにすることで、中間プランが「ちょうど良い」と映る
重要なのは、読者が不快に思わない「適切な差額や数字」の設定です。
あまりにも現実離れした価格の落差を提示すると、かえって不審がられるリスクがあります。
アンカリング効果を活用するときは「本当に読者のメリットにつながる形か」を意識しつつ、適度なアピールで納得感を演出するとよいでしょう。
損失回避の心理
損失回避の心理(損失回避バイアス)とは、人が「利益を得る喜び」よりも「損を回避する痛み」に強く反応する傾向をいいます。
同じ1000円でも「得する」より「失う」ほうが心理的ダメージが大きいため、文章でも「今だけ割引を逃すと、結果的に高額を払うことになる」という訴求のほうが響きやすいと考えられます。
ライティングでは「キャンペーン期間が過ぎれば定価に戻る」など、行動しない場合に被る損を強調する手法が定番です。
たとえば、
「この機会を逃すと二度と手に入らない限定特典です」
こう書かれていると、人は損失を避けたい心理から購買や申込みを前向きに検討しやすくなります。
ただし、損失回避を強く煽りすぎると、不安を過剰に与えてしまいクレームにつながるリスクもあります。
そのため、損失を意識させつつも「行動すれば回避できる」「安心できる代替策がある」と示すことで、読者が納得して行動を選びやすい形に導くのが理想的です。
初頭効果
初頭効果とは、人が「最初に接した情報」に強い印象や影響を受ける心理現象です。
記事を読む際にも、冒頭やリード文で興味を引かれるテーマや数字を提示すると、その後の読み進め方や理解が大きく変わってきます。
セールスレターの冒頭で「あなたが今抱えている悩みは○○ですか?」と読者の関心事に直球で触れる例も、初頭効果を狙う典型的なアプローチです。
- 最初の数行や見出しに「メッセージの核心」を盛り込む
- 「実績No.1」「驚異のリピート率90%」など、キーフレーズを冒頭に配置する
一方で、入り口は魅力的だったのに本文が平凡だと「最初だけか」と失望を招く恐れがあります。
そのため、序盤で読者を惹きつけたら、期待を裏切らない内容を継続して提供し、最後まで読ませる設計を行うことが欠かせません。
初頭効果を高める文章構成によって、読者が意識を向けやすくなるでしょう。
確証バイアス
確証バイアスは、人が自分の信じたい情報や先入観を裏付けるデータばかりを探し、反対の証拠を見落としがちになる心理傾向を指します。
ライティングでも、読者が「これが正しいはずだ」と思っているテーマに対して「やはりその通りだ」と肯定する内容を提示すると、より強く共感してもらいやすいです。
環境意識の高い層をターゲットにした商品で「この製品はエコ活動をさらに後押しします」と書くと「自分の価値観と合っている」と感じて関心を持たれやすい
一方で、確証バイアスを利用して誤った思い込みを強化するのは倫理的な問題が伴います。
適切なデータや根拠を提示しつつ、読者のニーズに寄り添う形で「あなたの考えをサポートする情報を提示する」スタンスが大事です。
読者が求める要素をあらかじめ調査し、それに合致する情報を分かりやすく示すだけで、文章の説得力が増すでしょう。
注意と記憶に関する心理(5つ)
読者の目を留めてもらい、最後まで印象に残る文章を作るには「注意」と「記憶」に関わる心理学の知見が役立ちます。
せっかく内容が良くても、最初の数行で離脱されてしまえば伝えたいメッセージは届きませんし、一度読んでもすぐに忘れ去られては効果が半減するでしょう。
注意を引くだけでなく、印象深い形で結びつけるテクニックを身につけることが、結果的にCVR(コンバージョン率)を押し上げるポイントにもなります。
ツァイガルニク効果
ツァイガルニク効果とは「完了していない事柄」のほうが頭に残りやすいという心理現象です。
「中断されたタスク」や「謎が明かされていないストーリー」などは、無意識のうちに続きが気になり、意識から離れにくくなります。
ライティングでは、記事の冒頭で読者の興味を引く問いかけをしておき、すぐに答えを明かさない方法がよく使われます。
たとえば、記事の冒頭で
「なぜ○○を実践するだけで売上が2倍に伸びるのか。その理由は後ほど詳しく解説します」
と書いておいて、少し引っ張ってから解答に移るイメージです。
そうすると、読者は途中で離脱せず、真相を知りたいがために読み進める可能性が高くなるでしょう。
ただし、あまりにも長く引っ張るとストレスを感じさせる場合もあるので、途中でヒントを適度に挟むなどの工夫が必要です。
ツァイガルニク効果を上手に取り入れると、読者の「先を知りたい」という好奇心をかき立て、ページ滞在時間やエンゲージメントを高めやすくなる点がメリットと言えます。
単純接触効果
単純接触効果(ザイオンス効果)とは、何度も触れる対象に対して「親近感」や「好意」が増していく心理です。
「商品名」や「ブランド名」を文章内で繰り返し自然に登場させるだけでも、読者は潜在的に「聞いたことがある」という印象を持ち始めます。
広告業界でも、同じキャッチフレーズを反復して認知度を上げる手法が定番で、ウェブライティングでも同様に使われます。
たとえば、記事のタイトル以外にも、以下の部分にキーワードを含めると効果的です。
- リード部分
- 見出し
- 本文(関連語も使う)
こういった所にさりげなくキーワードを含めることで、読者は無意識に馴染みを感じるようになるでしょう。
ただし、繰り返しが過剰すぎると不自然さや嫌悪感を与えるリスクがあります。
単純接触効果の恩恵を得るためには、読者にストレスを与えない範囲でキーワードやフレーズを提示するバランス感覚が求められます。
また、SNSやメルマガなど「複数メディア」で継続的に目に触れさせることも有効です。
一定期間をかけて接触回数を増やすことで、結果的に「認知度」と「好意度」の向上につながる可能性があります。
ピーク・エンドの法則
ピーク・エンドの法則とは、人がある体験を総合的に思い出すとき「最も感情が動いた瞬間(ピーク)」と「終わり際(エンド)」の印象によって全体の評価が左右される心理原則です。
たとえば、ライティングでは次のような使い方ができます。
- 中盤あたりで「インパクト」あるエピソードやデータを提示(ユーザーの感動的な成功談など)
- 最後の結論部分で前向きなメッセージと行動喚起を述べる
このように、記事の中盤あたりで読者の気持ちを強く揺さぶる「ピーク」を作り、終わり際に「好印象を残す結び方」をする構成が考えられます。
これにより、読者は「強く印象に残ったポイント」+「最後のまとめ」で記事全体を好意的に受け止めやすくなります。
反対に、終わり方が曖昧だったりネガティブな終幕を迎えたりすると、良い中身があっても「何だか後味が悪い」と思われ、全体評価も下がるかもしれません。
ピーク・エンドの法則を意識して文章を設計するときは、中盤に感情のピークを設定し、結末で気持ちを整えるという流れを作り、読後に良い余韻を残すのがポイントになるでしょう。
カクテルパーティー効果
カクテルパーティー効果は、多くの雑音が混在する中でも、自分に「関連性」が高い言葉や名前だけは際立って聞こえる心理です。
ライティングでも、読者が自分事だと感じる文言をタイトルや冒頭に盛り込むと「自分のための情報だ」と認識されやすくなります。
たとえば、
「忙しいワーキングマザーのみなさん必見!」
「65歳以上で高血圧の方はリスクあり!」
「上階がうるさいアパートに住んでる大学生は聞け!」
などと打ち出せば、該当する層は自然と注意を向けるでしょう。
また、ターゲットの具体的な年齢層や職業、住環境などに触れることで、他の情報に埋もれにくい訴求が可能です。
ポイントは、呼びかける対象を曖昧にせず「明確にイメージ」できる言葉を使うことです。対象を広げすぎると「自分には関係が薄いかも」と思われるかもしれません。
カクテルパーティー効果を利用するには、読者像をしっかり設定し、そのペルソナが「これは私の話だ」と思うようなキーワードを冒頭や見出しに入れるテクニックが重要です。
突出効果
突出効果(フォン・レストルフ効果)とは、多くの類似情報の中にあって「目立った特徴を持つ要素」が強く記憶に残る現象を指します。
同じようなデザインが並ぶ中で「一つだけ色や形が異なる」と、意識がそこに集中しやすくなるのもこの効果です。
たとえば、コピーライティングにおいて、
- 「唯一の○○」というフレーズを盛り込む
- 見出しの一部だけ別色で強調する
などの方法で「他にはないポイント」を際立たせることも有効です。
競合商品がひしめく市場で「差別化」を強く印象づけることで、読者の心に残りやすくなるでしょう。
ただし、突出効果を狙って装飾や強調を乱用すると、全体が散漫になって逆に注意を奪われてしまう恐れもあります。
重要なのは、読者に伝えたい「核心情報」をどこに置くかをよく考え、最も見せたい要素のみを強調することです。
[char no=”2″ char=”トール”]そもそも「魅力的なオリジナリティ」がなければ空回りになるので、特筆すべき強みやデータがあると効果的です![/char]
共感の形成(3つ)
商品やサービスを紹介する際、読者が「自分ごと」として捉えやすい文章だと心理的ハードルは下がります。
人は自らの「経験」や「感情」と通じる部分を見いだすと、心を開きやすくなり提案への理解も深まります。
また、読者の悩みを具体的に代弁することで「自分の状況を知っている人なんだ」と感じてもらえる点も、共感のメリットです。
ストーリーテリング
ストーリーテリングは、物語形式で情報を伝えることにより、読者が感情面で深く巻き込まれる効果を狙う手法です。
成功事例や失敗談などを「主人公の変化の軌跡」として描くと、人は登場人物に共感しやすくなります。
たとえば、サービス利用前後の状況をビフォーアフターで示し「まるで自分のことのようだ」と感じさせることで、強い説得力が生まれます。
- 具体的なエピソードやセリフを入れる
- 感情の起伏を丁寧に描写する
ただし、あまりに演出過剰で現実離れしていると「作り話では?」と疑われるかもしれません。
読者が身近に感じられる範囲でストーリーを組み立て、最後に「同じような課題を抱えるあなたにも、この変化が期待できる」とつなげる構成が理想的です。
ストーリーは共感を呼び、購買や行動喚起への強力な後押しとなります。
共感(感情移入)
共感(感情移入)とは、読者の抱える悩みや欲求を代弁し「あなたの気持ちを理解しています」というメッセージを伝えることです。
そして、共感を得るには、漠然とした表現よりも「細部に踏み込んだ描写」が有効です。
ターゲット読者が実際に体験していそうな場面や心理を正確に捉えるほど、読者には「まさに自分のことだ」と思わせやすくなるでしょう。
たとえば、ダイエットの記事なら
「仕事終わりにコンビニで手軽なものを買ってしまい、気づけば体重が増えていく」
といった日常のリアルなシーンを描くと、読者は「それ自分もやってる」と感じてくれます。
このように、具体的なシチュエーションを書くことで、読者の感情移入が深まりやすくなります。
ただし、表面的に寄り添う言葉を並べるだけでは、逆に不信感を招くリスクもあります。
本当にターゲットの悩みを理解している姿勢を示しつつ、その上で「解決策」を提案する流れを構築することで、読者の納得感と行動意欲をより強く引き出せます。
ミラーリング
ミラーリングは、相手の言葉遣いや仕草を「鏡のように真似る」ことで、心理的距離を縮めるテクニックとして知られます。
ライティングで使用する際には、読者のよく使う表現や価値観を文章に取り込むことで「自分と同じ感覚を持った人が書いている」と思ってもらう狙いがあります。
ターゲット層が多用する「SNSのハッシュタグ」や「流行の言い回し」を適度に用いる方法が一例です。
- ターゲットのライフスタイルや興味にあわせた「言葉選び」
- 年齢や悩みの深さに合わせた「文章のトーン」
- 若者が使う言葉を無理に使わない
読者が「自分の気持ちを共有している仲間だ」と感じてくれると、商品やサービスの購入にも前向きになりやすいです。
さらに、ストーリーテリングと組み合わせると、より強い効果が期待できます。
結局のところ大切なのは、読者の言語感覚を尊重しつつ、押しつけがましくならない範囲で寄り添うことです。
行動喚起と行動経済学の原理(4つ)
最終的に読者が購入ボタンを押す、問い合わせフォームに入力する、メール登録をするなどのアクションを起こすかどうかは、文章構成や誘導手法に大きく左右されます。
行動経済学では「フレーミング効果」「デフォルト効果」「ナッジ」「デコイ効果」などが特に有名です。
これらの原理をライティングに取り込むと、読者がよりスムーズに選択へ進むよう設計できます。
フレーミング効果
フレーミング効果とは、同じ情報でも「提示の仕方」によって受け手の印象が変わる心理です。
「成功率90%」と「失敗率10%」は数字こそ同じですが、前者はポジティブ、後者はネガティブなイメージを与える典型例となります。
文章中で結果やリスクをどうフレーミングするかで、読者の意思決定は大きく左右されるでしょう。
たとえば、
「今ならこの商品で○○円得します」
と示すのと、
「使わないと○○円損します」
と伝えるのでは、読み手が感じるインパクトがかなり異なります。
ポジティブフレームで希望を抱かせたい場合と、ネガティブフレームで危機意識を高めたい場合を、状況に合わせて使い分けると効果的です。
フレーミング効果を活用する際には「過度な煽り」や「誤解を招く表現」に陥らないようバランスを取りながら、読者が欲している情報を正しく伝えることを心がけましょう。
デフォルト効果
デフォルト効果は、あらかじめ設定されている選択肢を「人はそのまま受け入れやすい」という心理を指します。
人は「面倒を避けたい」心理が働きやすいので、初期設定を変えないまま流れに乗りがちです。
- メルマガ登録フォームで「最新情報を受け取る」にチェックを入れておくと、わざわざ外して登録する読者は少ない
- 複数の選択肢を提示する際に「おすすめプラン」を初期設定しておくと、そのプランが選ばれやすくなる
このように、ユーザーが「余計な思考や手間をかけず」に行動できるよう設計することは、ストレスの軽減にもつながります。
一方で、デフォルト効果を悪用して不利益を被らせるような設定は、信頼を損なう可能性が限りなく高いです。
理想は、読者にとってメリットが大きい選択肢を自然にフォローできる形であり、その結果として登録や購入を後押しするというアプローチが望ましいでしょう。
ナッジ(柔らかい誘導)
ナッジとは、環境や選択肢の「提示方法を少し整える」だけで、人の意思決定を上手に誘導する考え方です。
強制ではなく、自発的に「やってみよう」と思わせる点がポイントになります。
たとえば、ライティングでの一例として、
「もし今すぐ始めたら半年後どう変わると思いますか?」
といった問いかけで、読者に未来のメリットをイメージさせる手法が使われます。
具体的なイメージを描かせることで、行動に移す確率が高まるでしょう。
その他にも、
購入ボタン付近に「すでに○○人が申し込み済み」と小さく表示しておく
これだけでも、社会的証明と組み合わせたナッジとして機能しやすいです。
読者が自分の意志で最良の選択をしたと感じられるよう、過剰に押し付けずあくまでサポートする形を維持することが大切です。
ナッジは政府の政策にも取り入れられるほど注目されている概念ですが、ライティングの場面でも読者に「損しない選択」を気軽に選ばせる環境づくりとして有効となるでしょう。
デコイ効果
デコイ効果とは、意思決定を促したい選択肢を「相対的に魅力あるよう見せる」ために、わざと比較対象として微妙な選択肢(デコイ)を加える手法です。
価格設定で例えると、ライト・スタンダード・プレミアムの3つのプランを用意し、あえてプレミアムプランは割高に見えるようにすることで、スタンダードプランが「コスパが良い」と感じられる現象が典型的です。
このとき、
- 各プランのメリットを箇条書きで並べて可視化
- デコイ(微妙な選択肢)の存在を自然に配置
こうすることで、より効果が発揮されるでしょう。
さらに、読者が「自分の判断でお得な選択をした」と思えるため、満足度も高まりやすいとされています。
ただし、あまり露骨だと「これは誘導だ」と警戒されるリスクもあります。
読者が「自分で納得して選びやすい」形に留めつつ、主力商品やサービスへの誘導を意識した設計を行うのが理想です。
デコイ効果は「アンカリング効果」や「デフォルト効果」とも組み合わせやすいため、総合的に価格戦略を考える際に有用な心理原理だといえます。
ライティングに心理効果を使うときの注意点
心理学的な手法は、読者の決断を後押しする強力な力を持ちますが、その分使い方を誤ると「操作されている」という違和感を与えてしまうリスクがあります。
読者にとってメリットのある誘導であれば信頼関係を深められますが、逆にデメリットを被るような誘導は大きな反発を招くでしょう。
そのため、心理効果を活用する際は「倫理観」と「正確な事実確認」を徹底することが重要です。
過度に煽らない
「恐怖訴求」や「損失回避の心理」は強力ですが、必要以上に煽ると読者に不信感を与えやすくなります。
たとえば「今行動しなければ人生が終わる」という極端なフレーズは、一時的には興味を引いても、後から「大げさすぎる」と思われるリスクが高いです。
ライティングでは、危機感を伝える場合でも必ず「具体的な回避策」や「サポート体制」を合わせて紹介し、安心へ導くバランスを保つ必要があります。
過度な煽りをしてしまうと、
- 広告ガイドラインなどにも抵触する可能性がある
- クレームやペナルティにつながることもある
といったようなリスクにつながります。
読者の心を動かすために恐怖や不安を利用するならば、裏付けを示しつつ冷静な視点を添えて、誇張や脅迫的な言い回しに陥らないよう注意しましょう。
あくまでも「解決策を提示するための前段階」としての危機感の共有であり、読者を必要以上に怯えさせるのは望ましくありません。
結果として、適切な範囲の煽りは行動を促しますが、行き過ぎると逆効果になることを忘れてはならないです。
事実を歪曲しない
ライティングで統計や調査結果を引用する際、数字を都合のいいように切り取ったり、誤った比較を用いたりすると、長期的には信頼を大きく損ないます。
公的機関のデータ(例:総務省、厚生労働省など)を使う場合も、元のソースを明確に示し、数字の解釈を正確に行うことが不可欠です。
たとえば、
「厚生労働省の令和○年調査(https://www.mhlw.go.jp/)では、X%が該当」
などのように、具体的に明記すると読者は情報の裏付けを確認できます。
逆に、根拠不明のデータや「○万人が絶賛」というような抽象的な表現だけを繰り返すと、読者は疑問を抱きやすくなるでしょう。
また、確率やリスクについて明らかに誇張して書くことも問題です。
読者が後で真偽を調べる時代だからこそ、記事全体の信頼性が揺らがないよう事実に基づく表現を徹底するべきです。
効果測定をする
心理学的なテクニックを盛り込んだだけで満足するのではなく、本当に効果が上がっているかを検証し、改善を繰り返すことが大切です。
具体的には、
- A/Bテストで見出しを変えてクリック率を比べる
- コンバージョン(購入や登録)数が増減したポイントを分析する
といったように、客観的なデータを見て効果があったかどうかを判断します。
心理効果はターゲットや時期によって効き方が異なる場合もあるため、定期的な検証とリライトが必要になるでしょう。
実際、心理学的理論は万能ではなく、読者の属性によっては逆の反応が出るケースも考えられます。
だからこそ「PDCA」を回す継続的なアプローチが必須です。